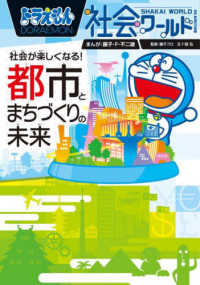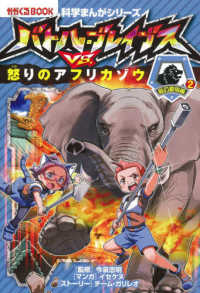内容説明
月刊誌『第三文明』の好評連載、待望の書籍化!5年間に綴った珠玉のエッセー47篇を収録。
目次
二〇一五年(南相馬に転居した理由;台所の正方形の窓 ほか)
二〇一六年(南相馬での年越し;教壇に立つ ほか)
二〇一七年(他者を希求し、受け容れられるように;先生の雅号は「明雨」 ほか)
二〇一八年(良い本との出会い;北海道へと旅立つ息子 ほか)
二〇一九年(ニューヨークでの最期の暮らし;山折哲雄さんとの対談 ほか)
著者等紹介
柳美里[ユウミリ]
小説家・劇作家。1968年、茨城県土浦市生まれ、神奈川県横浜市育ち。高校中退後、劇団「東京キッドブラザース」に入団。俳優を経て、1987年、演劇ユニット「青春五月党」を結成。1993年、『魚の祭』で、第37回岸田國士戯曲賞を受賞。1994年、初の小説「石に泳ぐ魚」を『新潮』に発表。1996年、『フルハウス』で、第18回野間文芸新人賞、第24回泉鏡花文学賞を受賞。1997年、「家族シネマ」で、第116回芥川賞を受賞。著書多数。2015年から福島県南相馬市に居住。2018年4月、南相馬市小高区の自宅で本屋「フルハウス」をオープン。同年9月には、自宅敷地内の「La MaMaODAKA」で「青春五月党」の復活公演を実施(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちゃちゃ
108
心に沁みる良いエッセイだった。声高に原発の非人道性を叫ぶのではなく、まず自らの役割(使命)を考える。2015年4月、柳美里さんは住み慣れた鎌倉から福島県南相馬市に転居。福島第一原発から16㎞地点の「警戒区域」に書店を開き、地元の高校生たちと演劇集団を立ち上げた。「『他者の痛み』に責任を持つ」ためには、まずそこで暮らし苦楽を共にすることが一番だと考えた。「生活の中にこそ、絶望を擦り抜ける小道がある」在日という自らの痛みと共振させつつ、その「小道」を作家・演劇家として探る。彼女の覚悟と気概が心に迫る作品だ。2023/03/25
アキ
83
南相馬市、東日本大震災後の旧警戒地区。2015年鎌倉から息子と転居し、2018年4月本屋「フルハウス」を開店。その日々を書き綴った日誌。なぜわざわざそんなところへ転居したのか?それには彼女の理由がある。そこで本屋を開き、劇団を作り地元の高校生と共に過ごす。「わたしがこの世に存在する意味は、わたしという個の内にあるのではない。わたしが何をしたいのか、何をすべきなのかは、わたしが決めるべきことではない」。震災時、何があったのか知ったことには責任が伴う。知ったことの責任を背中から降ろさないという覚悟が清々しい。2020/05/13
竹園和明
41
「被災地に住む方々の苦楽は暮らしの中にあるのだから、暮らしを共にしなければその苦楽を知る事は出来ない」という思いから、鎌倉の持ち家を出て福島県南相馬に移住。そんな事出来ますか?。その心意気に感服至極。そして南相馬市小高駅前に集いの場としてブックカフェを開設。高校では道徳の授業を担当し、高校生らと演劇集団を立ち上げました。電車で県内外のあちこちへ出向くフットワークの軽さも驚き。人の痛みを知る著者の活動は、きっと南相馬に大きな大きな足跡を遺すでしょう。穏やかな文体で新たな日々を綴る、素晴らしいエッセイ!2023/04/10
彼岸花
33
柳美里さんが鎌倉から南相馬に転居して、来年でもう10年になる。時の流れの早さを感じつつ、彼女の決断力と精神力の強さには頭が下がる。全国的にも激減している本屋を経営、劇団を復活させ、作家の仕事も継続、フル回転状態だ。現在も活躍の領域を広げていることだろう。改めて感じたことは、「福島の原発事故は終わっていない」のだ。それにより、人々が分断されることがあってはならない。“「知る」ことに責任が伴う”という言葉がずしりときた。作者の実直な生き様と繊細な文章がとけ合い、私の心のひだに触れた。続編の刊行を期待したい。2024/06/18
鴨ミール
26
なんとなく毛嫌いしていた作家さんだったが、読んでみたら文章の力に圧倒された。 彼女は自分が何をやりたいかではなくて、縁によって導かれたように進んでいく。そのバイタリティーも凄い。鎌倉の家を売って南相馬に移住し、高校生たちや地元の人のためにと本屋を開き、演劇ユニットを復活させて、地元の高校生たちの胸のうちにある苦しみ、悲しみを演劇によって吐き出させる。いくつもの言葉をこの本からいただきました。他人に寄り添う人には、人が集まるんだなぁ。2021/01/21
-

- 電子書籍
- 巴がゆく!(1) フラワーコミックス
-

- 和書
- 限界集落と地域再生