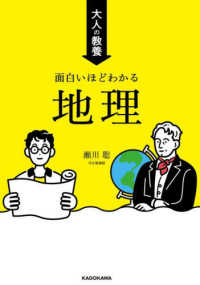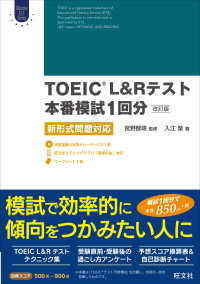出版社内容情報
茶道の本質は「おもてなし」の心。モデルのはなさんが、茶道の様々な分野の体験を通し、日本文化の奥深さや楽しさを紹介します。〈茶の湯を知れば、知らない日本が見えてくる〉
〈はなさんと一緒に学ぶ茶の湯の世界。そこには素敵なものがたくさん詰まっています〉
敷居が高くて堅苦しいと思われがちな茶道。でもその本質は?おもてなしの心? です。丁寧な振る舞いや相手への気遣い、お道具や料理、そして一服のお茶。そのすべてが「お客様に楽しんでもらう」ためのエッセンス。茶道は「想いをカタチにする」多くの分野でできています。この書籍は、幅広いジャンルで活躍するモデルのはなさんが、茶道を構成する各分野のプロフェッショナルとの対談や実際の体験を通して、日本文化の奥深さを読者にお届けする一冊です。また、はなさん自身が茶道を学び感じたことを綴るエッセイ「はなのお茶日記」も掲載。茶道を学んでいる人も、そうでない人も、きっと自分の知らなかった日本を知ることができますよ。
はな[ハナ]
著・文・その他
目次
茶事を知る―北見宗幸・裏千家茶道教授×はな
香を知る―大杉直司・山田松香木店×はな
表具を知る―中島実・表具師×はな
茶の湯菓子を知る―高家裕典・和菓子職人×はな
懐石を知る―岡哲夫・料理人×はな
趣向を知る―筒井紘一・数寄者・文学博士×はな
着物を知る―西村はなこ・「シルクラブ」店主×はな
樂茶碗を知る―樂篤人・陶芸家×はな
茶の湯釜を知る―大西清右衛門・釜師×はな
茶を知る―渡辺正一・一保堂茶舗×はな
漆器を知る―中村宗哲・塗師×はな
茶室を知る―田野倉徹也・数寄屋建築家×はな
茶会を開く―客筒井紘一・数寄者 亭主はな
著者等紹介
はな[ハナ]
神奈川県横浜市出身。二歳から横浜のインターナショナルスクールに通い、十七歳からモデル活動を始める。上智大学進学後もモデル活動を続け、テレビの司会、ナレーション、エッセイの執筆など活動の範囲を広げる。英語、フランス語に堪能(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MI
ochatomo
ミッチ
Risa
ミー子
-
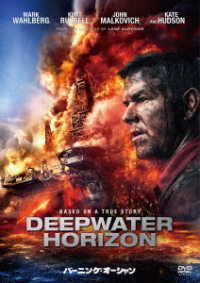
- DVD
- バーニング・オーシャン