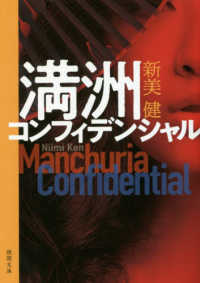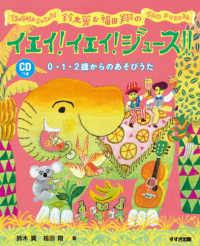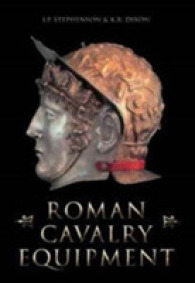出版社内容情報
珠光が、利休が、織部が、石州が……。茶道史上、不可欠の史跡が随所に! 奥深い奈良・大和路の茶文化がわかる1冊。
〈奈良の茶を知らずして、茶の湯は語れません〉
奈良市および奈良県内の茶の湯に関わる史跡や名勝、寺社を、平城京の時代から現代まで歴史を追って紹介。各史跡にゆかりのある茶人や茶道具、エピソードについて最新の情報を交えて案内します。京都・大阪との交流を持ち、茶道史上、重要な歴史を持つ奈良・大和路の茶の湯文化を、気鋭の茶道史研究家である著者が独自の視点で探訪していきます。
【著者紹介】
神津朝夫 1953年、東京生まれ。早稲田大学卒業、帝塚山大学大学院博士後期課程修了。博士(学術)。日本文化史・茶道史を専攻。著書に『千利休の「わび」とはなにか』『茶の湯の歴史』(共に角川選書)、『山上宗二記入門』(角川学芸出版)、『長闇堂記・茶道四祖伝書(抄)』(淡交社)、共著に『茶道学大系 第二巻 茶道の歴史』(淡交社)など。
内容説明
どこよりも深くて長い「茶の湯とのかかわり」。奈良市および奈良県内の茶の湯の史跡を、古代から現代まで時代を追ってご紹介。ゆかりのある茶人や茶道具、エピソードについて、最新の情報を交えながら案内します。
目次
1 茶の湯以前の奈良と茶―奈良~鎌倉時代(平城京と茶(平城宮跡・唐招提寺)
奈良時代の料理と菓子(長屋王邸跡)
東大寺と栄西(東大寺)
東大寺と栄西(東大寺)
西大寺の大茶盛(西大寺))
2 茶の湯の成立と奈良―室町~織豊時代(大乗院庭園と今西家書院(興福寺)
珠光と古市播磨(称名寺)
中坊屋敷と松屋(奈良町)
松永久秀の多聞城(多聞城跡)
今井町と今井宗久(橿原市今井町)
戦国の郡山城(大和郡山市)
桜の吉野山(吉野町))
3 奈良に広がる茶の湯―江戸時代以降(春日大社と久保権大輔(春日大社)
大名たちと茶の湯(赤膚山・田原本他)
大和小泉と片桐石州(慈光院)
奈良晒茶巾と高山茶筅(生駒市高山町他)
依水園と裏千家(依水園))
著者等紹介
神津朝夫[コウズアサオ]
1953年、東京生まれ。著述家。早稲田大学大学院・帝塚山大学大学院修了。博士(学術)。日本文化史・茶道史を専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。