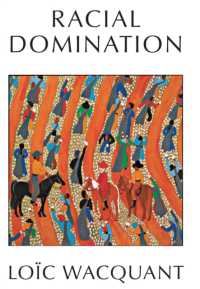出版社内容情報
本書は、樂家当代・樂吉左衛門が、樂焼の誕生から今日までをみずから解説した決定版。
内容説明
「楽焼」、それは今から四〇〇年前、茶の湯のためにはじめられた日本の焼物…楽茶碗の世界。初歩的な疑問に答えながら、この本ははじまります。グラフィカルに楽しみながら、気楽にページを繰ってみるうちに、「楽焼」という陶芸の全容が見えてくる本。
目次
1章 楽茶碗ってなんだろう(楽茶碗の誕生;楽茶碗の特色 ほか)
2章 楽焼のルーツを探る(ルーツは中国・明時代の三彩陶;陶片にうかがう楽焼の広がり ほか)
3章 楽家歴代―一〇〇年ごとに見る楽家の道統(長次郎から常慶へ;常慶のバロック ほか)
4章 付(楽家年表;楽歴代のプロフィール ほか)
著者等紹介
楽吉左衛門[ラクキチザエモン]
楽家十五代当主。1949年、楽家十四代・覚入の長男として京都市に生まれる。東京芸術大学彫刻科卒業。2年間のイタリア留学ののち、1981年十五代吉左衛門を襲名、現在にいたる。87年プリンストン大学「ヴィジティングフェローシップ」、92年「日本陶磁協会金賞」、93年「MOA岡田茂吉賞優秀賞」、98年「第40回毎日芸術賞」、2000年「フランス芸術・文化勲章シュヴァリエ」、01年「京都府文化賞功労賞」など受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
186
樂茶碗といったら、千利休が作らせた「侘茶」の茶碗、くらいしか知らなかったが、実に奥の深い器だった。樂家の15代当主が、初心者にもわかりやすく書いた入門書でもあり、写真をふんだんに入れた専門書でもある。初代・長次郎が始めた「手捏ね(てづくね)」。ロクロを使わず、粘土をひも状にして造形するのでもない、手でひねり出す樂茶碗のみの制作技法、だという。「手の姿がそのまま映し込まれている」ので国宝・弥勒菩薩座像の優しい手の表情に似ているともいう。小ぶりでいながら、「手のひらの中の宇宙」を感じる名器だった。2019/09/17
アキ
67
400年もの伝統を継承している樂焼。樂吉左衛門自身が著した入門書。栄西が伝えた喫茶の風習から約380年経ち、侘茶を完成する利休に頼まれた瓦職人・長次郎がはじめ、今年7月に16代吉左衛門の襲名があったばかり。樂美術館は訪れたことがあるものの、なぜ樂焼きと呼ぶのか?赤茶碗と黒茶碗の違いなどはこの本で理解した。なんといっても利休も使ったと思われる茶碗が今も残されているという事実。代々の特徴が述べられており、変容しながら現在がある。手のひらの中の口を開けた宇宙。さて16代はこれからどんな作品を生みだすのか?2019/09/15
♡ぷらだ♡お休み中😌🌃💤
33
千利休が理想の茶の湯茶碗を初代長次郎に造らせたことから始まる樂焼。創始以来450年、代々の当主が利休の佗茶の精神をくみ、京都で窯の火を守り続けてきた。篤人さんが十六代吉左衛門を襲名することをニュースでやっていたので読んでみた。樂家歴代の作品がカラーでしっかり紹介されているので、新しい作風を模索しながらも、伝統を継承しようとする姿が伝わってくる。樂美術館にいってみたくなった。2019/07/04
さっちも
12
利休が長次郎という陶工に、自分好みの侘茶の精神を表した器を焼かせたのが「樂焼」の起こり。それが今の時代まで一子相伝的に続いている。一樂、二萩、三唐津という言葉があり、茶人が珍重する陶器の順番なのだけど、お茶の世界で樂家の跡取りが担うプレッシャーというのが半端でない事が伺える。しかも、主体や自由を尊ぶ禅の精神から生まれた茶の湯文化だけに、樂家では先代の手法をただ真似ることは許されないというイケズな掟が存在する。時代と自己を手掛かりに新しい物を創作し、それでいてどの人間にも通底する不易流行という利休の精神と2017/09/11
Toshi
6
2017年に近代美術館「茶碗の中の宇宙」展、トーハク「茶の湯」展で、楽焼の代表作が一同に会した。どれも一見シンプルだが、見つめていると吸い込まれていきそうな深みがあった。本書はその楽焼の歴史と作品を、楽家の現当主である吉左衛門自らが解説する、豊富なカラー図版と相まって恰好の入門書である。2020/10/23
-

- 和書
- 医療事故訴訟の研究