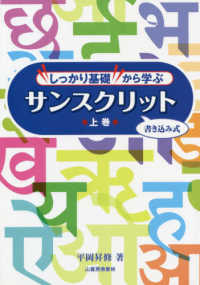内容説明
昨年注目されるCEFR(欧州言語共通参照枠)。本書は、CEFRが採用した「CAN‐DOリスト」形式に則り、新たに策定された日本人学習者の英語到達度指標「CEFR‐J」の概説書である。CEFR‐JのCAN‐DOリストの内容をレベル・スキル別に詳しく解説するほか、CAN‐DOリストの作成、指導への活用にも役立つ1冊。
目次
1 CAN‐DOリストの原典:CEFRとは?(CEFRができた歴史的な背景とは?;CEFRの理念である「行動指向アプローチ」とは?;CEFRが前提とする「複言語主義」とは? ほか)
2 CEFR‐Jを理解する(CEFR‐JとCEFRとの関係は?;CAN‐DOリストの表す能力とは?;CAN‐DOリストのディスクリプタの含むべき要素は? ほか)
3 CEFR‐Jを活用する(Pre‐A1レベルのCAN‐DOの特徴とその指導法とは?;A1レベルのCAN‐DOの特徴とその指導法とは?;A2レベルのCAN‐DOの特徴とその指導法とは? ほか)
著者等紹介
投野由紀夫[トウノユキオ]
東京外国語大学大学院教授。専門はコーパス言語学、第二言語語彙習得、辞書学。現在はCEFRのレベル別学習者コーパスをもとにした英語学習者のプロファイリング研究を中心に行っている。8年間にわたり、科研費基盤AでCEFRの日本の英語教育への適用を実証的に研究し、CEFR‐Jを発表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かおりんご
14
教育書。評価について勉強したくて読む。中学校以上向けだなぁ。さっと目を通して終わる。2020/08/08
Nobu A
1
「CEFRの意義と実践」ワークショップに合わせて購入読了。後半の英語の活用編は流し読み。「肯定的にデキル一部分を評価する」というのが印象的。そう言えば、高校の国語の授業中、疲れて最初から最後まで熟睡。終了ギリギリで目が覚め、他の学生は父についての作文を書き終えたところ。慌てて「私の父はいません。そんなこと聞かないでください」と書いて提出。嘘がバレて、こっぴどく叱られたが、これもストラタジーを上手に使ったということで、今なら評価できるのだろうかと考えた。そんなことないな(苦笑)。2015/06/26
Kazuki
0
図書館で借りた本 読了まではできず返却 系統だって書かれてはいるが読みづらかった2019/05/03
-
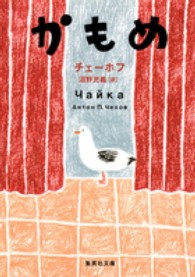
- 和書
- かもめ 集英社文庫