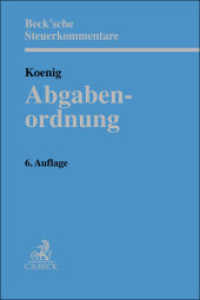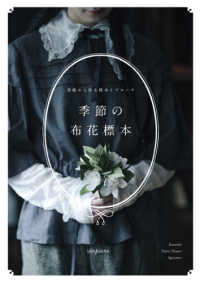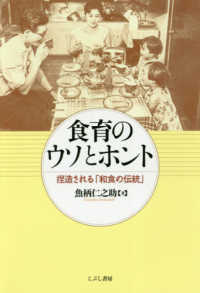内容説明
日本を代表する妖怪である天狗。しかし、その正体は、意外にも多くの謎につつまれている。天狗はどのように誕生したのか?天狗の鼻はなぜ高いのか?そもそも、天狗とは何者か?天狗イメージの源流を探り、その誕生の謎を解く、図像学の挑戦。
目次
第1章 天狗は空から降ってくる(空から降る怪異;生きていた中国の天狗)
第2章 初期天狗の誕生(天狗登場;天狗復活;比叡山と天狗)
第3章 『今昔物語集』の天狗たち(復活天狗の大活躍;幻影装置としての天狗;天狗説話のバリエーション)
第4章 天狗再登場のメカニズム(発生初期の天狗イメージ;「天狗さらい」の系譜;天狗の鼻はなぜ高い;密教と天狗;浄土教と天狗)
第5章 天狗イメージの源流を探る―海を渡った有翼の鬼神たち(雷神イメージの変遷;仏画のなかの鬼神たち;カルラのイメージ;日本に飛来した有翼鬼神;飛来するものたちへの視線)
著者等紹介
杉原たく哉[スギハラタクヤ]
1954年東京都生まれ。1989年早稲田大学大学院博士課程修了。早稲田大学文学部助手を経て、現在は講師。専門は中国古代美術史だが、専門の枠にとらわれず、日中のさまざまな図像を比較芸術の視点から幅広く研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のりたまご
10
天狗って何?もともとは中国で流星の事で、四足で犬のような吠える声(衝撃音)から「天狗」とよばれた。飛鳥時代に日本に伝わったが流星=天狗とはならずに、別の解釈が生まれるに至った。しばらくは沈黙していた天狗は、平安時代に妖怪として復活し、仏教世界を巻き込んで成長(?)していく。子をさらう猛禽類から、天狗の半鳥半人の姿がうまれ「天狗隠し」「天狗さらい」と呼ばれるように。また、そのイメージは鬼神や不死鳥カルラにある。仏教から古典までよく調べられていて面白かった。ホグワーツ魔法学校の教科書にも天狗が登場するらしい。2020/10/27
テツ
5
天狗の成り立ち。アマツキツネやらガルーダやらほとんど知っている内容ではあったけれどこの手の本が大好きなのでとても興味深く楽しく読めました。文化として洗練された八大天狗みたいな存在は本当に素晴らしい。修行の果てに輪廻の道を外れ解脱したかに思えたけれど魔道を歩んだため天狗道に迷い込んだ者達。いつか彼らが救われる日は来るのかと、幼い頃にぼんやりと天狗の成り立ちを聞いた日に思ったな。2015/06/25
竜王五代の人
4
平安時代後期に、ほぼ突如出現し、その時点でほぼ「烏天狗」だった日本天狗。その一方古代からずっと「天翔ける犬」のまんまの中国天狗。この天狗という名前が浄土教研究で発掘され、烏天狗じみた半鳥半人の図画イメージが合体し、比叡山を中心とする仏教界で生じたライバルを天狗と罵る習慣と合わさり……大陸からダイレクトで入ってくる環境でなかったことが生み出した異形としか言いようがない。「文字」と「読み」と「外見」の三つがネジレているという筆者の指摘は至極もっとも。2022/12/03
まづだ
3
天狗の「狗」って、犬ってこと?天狗のどこが犬なんだ?と、ふと疑問に思ったので読んでみた。古代中国では、天狗は隕石。落下の音と犬の鳴き声を重ね合わせたそうだ。それが日本に輸入され、天狗は進化を遂げる。天狗という妖怪の持つ意味と、その図像は独立して、また時には影響しあいながら進化を重ねる。その歴史は、農村の母の悲しみも、宗教対立も、曼陀羅もガルーダも組み込まれて複雑怪奇!いかに天狗という妖怪が人々にとって身近で、でもあやふやな存在だったのかがよくわかって面白いです。龍だとこうはいかないね。2012/03/15
福ノ杜きつね
2
お馴染みの妖怪・天狗。「天の狗」と表記されるにも関わらず、似ても似つかぬ鳥人様の姿で認知されているのは何故なのか。本書ではそのビジュアルイメージの成立に迫っていく。元来、古代中国で流星現象を指す言葉に、インドのカルラを源流として生まれた道教の有翼鬼神(主に雷神)、仏典にて「ウルカー(流星)」を天狗であると注釈したこと、猛禽類による乳児拐い、これらを包括した「天からの災い」を表現したものではないか、とするのが著者の見解である。複数のラインから重層的に共通項を探っていく手法は、説得力に満ちている。2024/06/04