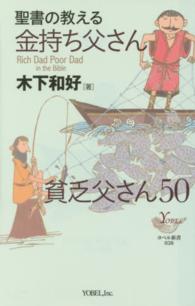- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(海外)
内容説明
中国の歴史書はどのようにして成り立ち、書き継がれたものであるか。その様子を見ていくと、それは歴史書の歴史であるだけではなく、まさにそこに人間の歴史そのものがある、と言いたくなるような重みを持って、我々に迫ってくる。
目次
第1章 『春秋』の虚実
第2章 『史記』の成立
第3章 「正史」の形成と展開
第4章 記録する側の論理
終章 北魏・国史事件の意味するもの
著者等紹介
竹内康浩[タケウチヤスヒロ]
1961年、青森県弘前市生まれ。1984年、弘前大学人文学部(東洋史専攻)卒業。1990年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程(東洋史専攻)単位取得退学。現在、北海道教育大学教育学部釧路校(東洋史)助教授。殷周青銅器及び『山海経』に関心を持ち、中国古代史を勉強中。また一方、歴史教育・歴史学習の意義について思索中
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ピオリーヌ
16
2002年の刊。あとがきより、「歴史を記録することをめぐっての人間の(特に権力の)意識について、主に関心を寄せてこの本を書いた」とある。主に『春秋』『史記』『漢書』『三国志』の成立について述べた内容。他、歴代皇帝の以上出生譚を比較した内容が面白かった。劉邦は神秘的な出生が語られ、三国~晋は現実路線、南北朝、北魏は再度神秘路線が復活し今後はこちらが主流になったと語られる。2025/08/27
ジュンジュン
10
奇しくも、最近読んだ「戦国武将、虚像と実像」(呉座勇一)とコンセプトは同じ。歴史書は書かれた時代、立場によって制約を受けるのは当然だが、官選で編まれた「正史」はバイアスの度合いが強い。儒教的道徳での評価が事実の記録より優先され、王朝の正統化につながっていく。2022/10/20
さとうしん
7
TLでしばらく前に正史の話題が出たので再読。『史記』『漢書』『三国志』『後漢書』が当初私撰の書であり、特に『史記』において、後代で言う稗史・野史的な要素を多分に含んでいることを思うと、正史と稗史・野史の区別に必要以上にこだわることは、史学史以外の文脈で果たしてどれほどの意味があるのかと思った。2016/06/27
サアベドラ
5
二次史料はなにかしらのバイアスがかかっているので、書いてあることをそのまま鵜呑みにしてはいけません、という初歩的なことがつらつら書いてあるだけ。そんな歴史学の入門書に書いてあるようなこと力説されましても困ります。タイトルから中国の歴史叙述のスタイルや思想の変遷を考察するのかを期待したが、そこら辺は論証が甘く、あまり参考にならない。アマチュアならともかく、著者は歴史学の助教授(執筆当時)なのだから、もっとレベルの高い話をしてほしい。一般向けと割りきっても、ちょっと手を抜きすぎじゃないかな。2011/04/12
赤白黒
4
著者の歴史学習への思いを述べた本だった。著者の言いたいことは終章に集約されていると思う。冒頭『春秋』から『史記』への流れ、『史記』と『漢書』の比較などは面白く読んだが、その後はエッセイのような冗長な文章で印象論を縷々述べるばかりで(帝王の異常出生譚は面白かった)、現代人の目線で過去の編纂物に筆誅を加える姿勢が鼻につく。洪秀全への評価にしても、『清史』が「載記」を設けて伝記を立てたのであればそこには当然編者の歴史観が反映しているはずで、その部分をもっと掘り下げてほしかった。全体的に歴史書への愛を感じない。2024/08/28
-

- 和書
- 多頭獣の話