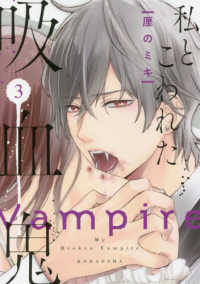出版社内容情報
三宅義藏[ミヤケヨシゾウ]
著・文・その他
内容説明
豊饒な「読み」の可能性を55の観点から浮き彫りに。
目次
「羅城門」を「羅生門」と変えたのは、なぜか。
実在した「羅城門」は、どのような門だったか。
暮れ方から物語が始まるのは、なぜか。
「下人」とは何か。
登場人物に名前がないのはなぜか。
「雨やみを待っていた」と書いて、後で言い直したのはなぜか。
「蟋蟀」は、コオロギかキリギリスか。
「旧記によると」という解説があるのはなぜか。
「仏像や仏具を打ち砕いて~薪の料に売っていた」という記述は何のためにあるのか。
実際にはいない「鴉」の描写があるのはなぜか。〔ほか〕
著者等紹介
三宅義藏[ミヤケヨシゾウ]
昭和29(1954)年、兵庫県生まれ。千葉県立高校の国語科教諭として、計43年間勤務。千葉県立千葉高等学校、千葉県立幕張総合高等学校など、計5校で教鞭をとる。国語教育を探究する一方、将棋部顧問としても活躍。女子団体戦で全国大会優勝に3回導く。現在、千葉明徳中学校・高等学校非常勤講師。平成3年から現在に至るまで、31年間にわたって大修館書店の国語教科書編集委員を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あいあい
3
高等学校の国語教科書の定番、芥川龍之介「羅生門」。高校生が疑問に思った55の論点ついて、「これはどういうことか」「なぜか」「なぜ作者は(語り手は)こう書いた(語った)のか」などなどと、高校生自身が何人かのグループで検討し発表した内容、教師たちの勉強会で出た意見を元にまとめてある。文学テクストは色んな読みが楽しめ、いろんな解釈がありうるのだということを教えてくれる。2022/11/05
とある下関
2
羅生門の素通りしていた表現、言葉の数々をほぼ全て網羅して考察しているのではないかという1冊。この本は必携だと思う。2025/12/03
うゑしま
1
これ、めちゃめちゃおもしろい。「羅生門」は短編で国語教科書でもよく取り上げられ、自分も例に漏れず高校の授業で学んだ記憶があるが、かなり強く印象に残っている。この本のような授業、受けたかったな。2023/02/01
takao
0
高校授業の学習から2025/09/03
稟
0
現場と文学研究を架橋する本。随所で触れられているがあくまでもベースは羅生門の研究論文なのだろうが、元ネタについては特に言及されていない。学術書としてはさておき、現場の教員にとっては垂涎の一冊と言えるだろう。もちろん本書に書かれているもの全てを許容するのはアナーキーだが、生徒の読みのバリエーションとして把握する分には絶好の著書ではないだろうか。2023/04/21
-
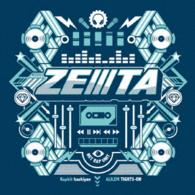
- CD
- らっぷびと/ZEⅢTA