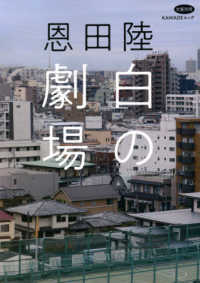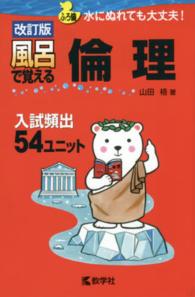出版社内容情報
「言語の教育」と「文学の教育」の狭間で揺れ動いてきた戦後の国語教育における文学の扱いの変遷を丹念に検証。今後のあり方を問う。
内容説明
「論理国語」「文学国語」はなぜ生まれたのか。世紀の大改革といわれる高校国語の科目再編。その背景には、戦後の国語教育の歩みの中で繰り返し論議を呼んできた、「言語の教育」と「文学の教育」の相剋があった!
目次
第1章 戦後初期の国語科は何を目指したのか―言語教育という黒船
第2章 戦後国語教育は文学に何を求めたのか―文学の鑑賞と人間形成
第3章 文学教育はどう展開したか―文学科を求めて
第4章 文学教材の指導はどのように確立したのか―高度経済成長と読解指導
第5章 定番教材はどう読まれてきたか―「羅生門」「走れメロス」「ごんぎつね」
第6章 国語教育はどのように変化を迫られたか―知識基盤社会の中で
著者等紹介
幸田国広[コウダクニヒロ]
1967年、東京都生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。博士(教育学)。国語教育史学会運営委員長。NHK高校講座(Eテレ)「国語表現」番組委員(監修・出演)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
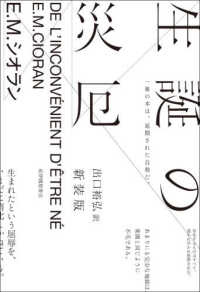
- 和書
- 生誕の災厄 (新装版)