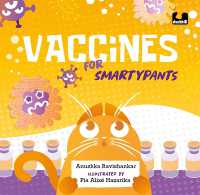出版社内容情報
今や世界各国で遊ばれる麻雀。その起源と、それぞれの国特有の「麻雀」になっていく課程を探る。貴重な文献や写真多数掲載!
大谷 通順[オオタニミチヨリ]
内容説明
本書では、わたしたちが知る「麻雀」が、いつ、どこで、どのように誕生したかを探りました。「ポン!」「チー!」という中国風のかけ声、牌の表面に彫り込まれた漢字と神秘的な文様…あたかもはるか昔から存在していたゲームのように錯覚していませんか?ところが、その歴史は意外に浅く、わずか90年前にはその呼び名さえ定まっていなかったのです…。中国・アメリカ・日本に眠る貴重な資料を掘り起こし、「麻雀」誕生の真実にせまる、初めての試み!
目次
序章 よび名と、それが示すもの(「マージャン」への統一;中国における呼称;誤認された麻雀;絵画にみる麻雀)
第1章 社交の麻雀(アメリカの熱狂;一九二二年―ブームの発火点;ルーズなタイトル?)
第2章 麻雀の核心(麻雀テーブル;特徴はポン;ドミノの「〓(ほう)和」)
第3章 租界が彩る麻雀(プレーの情景;麻雀と伝説)
第4章 麻雀の起源(記号の変容;変わり種牌;遊戯法の特徴)
著者等紹介
大谷通順[オオタニミチヨリ]
1956年生れ。中国文学者。北海道大学大学院文学研究科博士課程中退。北海学園大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
31
わからないことはしっかりわからないと言ってくれることって気持ちいい。中国文学者が前史を丁寧にたどる麻雀の歴史。なんと、索子は紐に銭を通した形だったとは!清代の都市で遊ばれた中国式ドミノやカードゲームが租界、アメリカ、日本を通して一つの体系になっていく様。遊郭の一室での点数計算がリアル。代走がすでにあるのも面白い。◇1920年代、以前に読んだ、寄席からの漫才の誕生や新聞紙上での風刺絵からのコママンガの形成とかぶる。近代社会の成立史だ。◇なんで白發中なのかとか、東南西北なぜ逆回りなのかとか、謎はまだまだ残る。2017/01/22
らむり
24
いらない内容が多かったような。。2016/09/17
どらがあんこ
9
麻雀そのものの話というより麻雀をめぐるものの話。麻雀の近代、というところか。ネット麻雀の普及によって麻雀のこれからどう変化するのか気になる。2020/12/27
Mzo
7
麻雀というゲームが普及するまでの歴史を、丹念に追っている。意外と麻雀そのものの歴史は浅かった…。伝説がどのように作り出されるか、というのも興味深く、面白く読めました。よし、これで、麻雀が少しは強くなったはず!2025/05/28
さとうしん
7
麻雀の中国での源流、アメリカでのブームと規格化、日本での受容と紹介など、委細を尽くした解説となっている。「筒子」「索子」「万子」のデザインがすべて銭に由来すること、夏目漱石『満韓ところどころ』の、現地での麻雀遊びに関するものとされる記述が、実は今で言う麻雀ではないのではないかというツッコミなどが個人的な読みどころ。2016/09/21
-
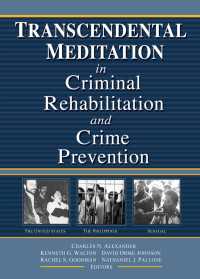
- 洋書電子書籍
- Transcendental Medi…