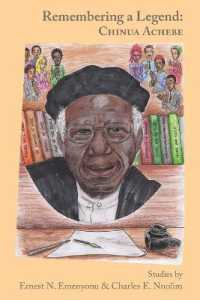内容説明
サルからヒトへの進化の過程で、ことばはどのようにして誕生したのか?発達過程で子どもたちはどのようにしてことばを身につけるのか?これら言語研究のコアとなる難題について、サル学、子ども学のエキスパートである生物学者と脳とこころとの関係からことばを研究してきた認知科学者が検討を加える。
目次
第1章 生物の進化からことばの起源を探る(サル学からわかること;言語と遺伝子 ほか)
第2章 ヒトの行動・認知・発達とことばの関係(ヒトの言語能力の成り立ち;模倣から共感へ ほか)
第3章 ことばの変化(社会生活とことば;コミュニケーションの変化)
第4章 ことばの科学に求められるものとは何か(理論言語学の場合;言語行動分析の場合 ほか)
著者等紹介
正高信男[マサタカノブオ]
1954年生まれ。大阪大学卒業。大阪大学大学院博士課程修了。学術博士。現在、京都大学霊長類研究所教授。専門は認知神経科学・比較行動学・霊長類学
辻幸夫[ツジユキオ]
1956年生まれ。慶應義塾大学卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程修了。現在、慶應義塾大学教授。専門は認知科学、意味論、言語心理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。