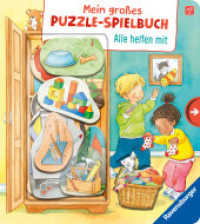出版社内容情報
"ピジンやクレオールと総称される“新しく生まれた言語""を、成立過程からその後の変化まで、現地において実体験、観察し、人間言語の始まりや子供の言語習得のメカニズムを解明する。"
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
2
植民地の第1世代は、植民化する側の言語をバラバラに習得する(ピジン語)が、第2世代は教えられずとも独自の文法を用いて会話を始める(クレオール語)。このクレオール化の動きに、著者は何らかの生得的な言語モデルの働きを仮設し、チョムスキー理論を援用しながら探究する。チョムスキーが赤ん坊が短期間に言語習得する点に注目し、人間は言語能力を生得的にもつと仮設した言語の生得説を音韻論に拡大する著者は、チョムスキー理論の混同と批判されたが、人間はタブラ・ラサ(白紙)から言語を学ぶという経験論モデルを転倒する実例を示した。2017/04/08