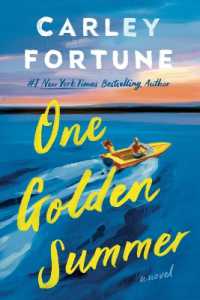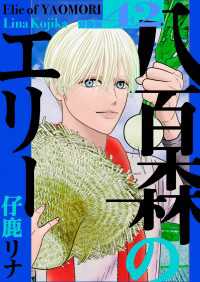出版社内容情報
大竹弘和[オオタケヒロカズ]
著・文・その他
目次
第1章 学校を「ハコモノ」と考えて教育格差解消(一九七五年までは向上した子どもの体力;体力の二極化とは何か? ほか)
第2章 地域を活性化する「ハコモノ」 それが学校(学校が一七〇日も使われていない現実;官民連携で容積率の大幅アップも可能に ほか)
第3章 「地域交流デパートメント」とは何か(廃校ではなく生きている学校という「ハコモノ」で;「地域交流デパートメント」の全貌 ほか)
第4章 民間事業者を活用した「未来の学校」(「学校教育」と「社会問題を解決するソフト」をセットで;数百人の子どもと教員のみが占拠する学校 ほか)
著者等紹介
大竹弘和[オオタケヒロカズ]
1955年、東京都に生まれる。神奈川大学人間科学部教授。筑波大学大学院修士課程修了(スポーツ経営学専攻)。専門は、官民連携の教育論、公共政策とスポーツ論、スポーツ産業論。総合システム研究所代表取締役。スポルテック(スポーツ健康産業における日本最大のコンペンション)実行委員、日本スポーツクラブ協会評議員も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ニッポニア
31
なかなか読み応えありました。あるものをとことん利用する、という姿勢は極めて現代的です。以下メモ。学校が170日も使われていない現実。顧客の利益に対して最大の努力をするクライアントインタレスト。孤食がもたらす孤独の解消に、学校レストラン。このハコモノが新たなビジネスチャンスに結びつく。地域交流デパートメント。2022/09/10
こも 旧柏バカ一代
16
学校の校舎を有効利用する提案の本だった。学校側からしたら言いたい事が多々あるだろうが、このままではジリ貧なのは確実だし校舎は予算を大量に食う存在にもなっている。それを打開するために学校を地域に開放して利用料金を徴収して、修繕維持費を税金からだけではなく、校舎を利用する市民からも貰うという想定。でも、刑務所か?刑務所と学校をか、、、初犯の人なんかには良いのかも?もちろん刑務官がしっかり監視するのもあるけど大胆だよな。山口県でやってるらしい。そういう実際にやってる人達から実際に話を聞くのも良いのかも知れない。2022/08/21
izw
5
小中学校は統廃合に廃校となる校舎が多く、その活用についても課題ではあるが、学校として使っているスペースそのものものも稼働率が低く、もっと活用すれば地域活性化につながるという主張。まあそうかもしれないと思えた。ただ、公務員は利益感覚がないからダメ、民間に任せることで効率よく活用できるという安直な考えには危険さを感じた。2023/03/22
こすも
4
小学校に行って椅子に座ってみれば、本書にかかれていることが無理なことがすぐにわかると思う。 放課後の塾の活用も某自治体でモデル事業として行っているが、学校を利用しても塾側のコストがかかりすぎるのでうまくいっていない。 民間も人材不足なんだから講師を余計に確保して学校に派遣する費用がバカにならないことは、少し考えればわかることだと思う。2025/02/13
Sanchai
2
【Kindle Unlimited】廃校の再利用という話ではなく、今も使われていて施設が老朽化している学校のリデザインの話だった。また、後半は政治家による賛辞のオンパレードが続き、それでページ数がかさ上げされている感が強い。「日本を救う」かどうかはともかく、主張そのものの方向性はそうなのかもなと思う。でも、何校ぐらいをまとめたら民間委託もペイするのかとか、そうやって広域の運営をされたら、意外と「地元」の雇用創出にもつながらないような気もした。2023/05/02