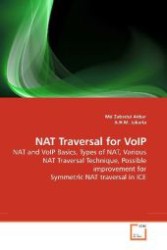内容説明
江戸時代の薬の使用の実態を知るには、印籠が日常どのように使われていたかを知らなければならない。本書では印籠の調査をきっかけとして、江戸時代における薬のある暮らし、医療、薬の供給側の事情などを探索して、印籠と薬、そしてその包装を取り上げた。
目次
第1章 印籠は薬の容器―薬携帯の習慣と包装
第2章 印籠の構造と薬の容器―包装・容器の技術
第3章 薬のある暮らし―薬はどのように使われていたか
第4章 医療と薬の製造販売―医師と薬を作った人たち
第5章 紙が売薬を広めた―薬の包装と紙の利用
第6章 文字社会の成立―包装による情報の伝達
第7章 「薬の気」を守る―薬の品質と包装
第8章 蘭学がもたらした薬のガラス瓶―近代包装の夜明け
第9章 薬包装の原点を築いた人たち―曲直瀬道三と貝原益軒
著者等紹介
服部昭[ハットリアキラ]
1936年大阪市生まれ。名古屋市立大学薬学部卒、薬学博士。神戸大学法学部二部卒。藤沢薬品工業(株)を経て、現在、小西製薬(株)総括製造販売責任者。技術士(包装技術)。1999年~2008年、龍谷大学経営学部非常勤講師。日本薬史学会評議員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。