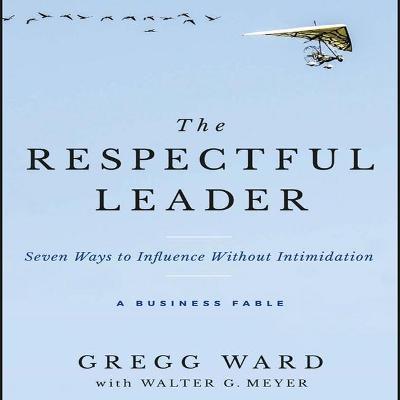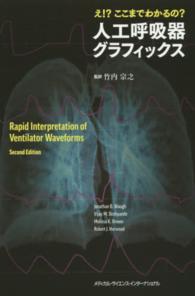内容説明
民俗芸能の宝庫、若狭に残された史料を渉猟し、中世から近世において、村々で盛んに演じられた、能・翁の変遷を記録した貴重な研究。
目次
第1章 寛文の「小浜藩寺社書上帳」に見る若狭の翁・猿楽能の分布(「小浜藩寺社書上帳」に見る神社の神事祭礼と寺院;翁の村と猿楽能の村 ほか)
第2章 寛文以降の史料に見える猿楽能と能禄米(寛文・元禄・明和の史料;旦那場と能禄米)
第3章 帰山大夫の翁猿楽から倉大夫の猿楽能へ(中世の猿楽;倉座の成立とその後の活動 ほか)
第4章 江村家の翁旦那場と座の衰退(江村家の翁を中心とした旦那場;倉座の困窮)
著者等紹介
山田雄造[ヤマダユウゾウ]
1949年生まれ。1972年~2009年3月福井県内高等学校に勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
6
「囃子方や地謡方を含めて多くの人員を要する能や翁は、倉座を中心とした専門の一座によって、用意された舞台で演じられた。その他の神事は専従の神主がいる大社は別にして、多くの村々では中世の伝統を受け継いだ惣村の宮座グループが勤めたのであろう」「神楽を行う神社が非常に多く、神輿もかなり出されている。農耕儀礼とのかかわりをうかがわせる田植えのまねごとや田楽も見られる。流鏑馬や的射の神事も…残っている」「17世紀の段階で若狭の九割の村々で翁が演じられていた…こうした流れは14世紀には始まっていたものと思われる」2015/11/26