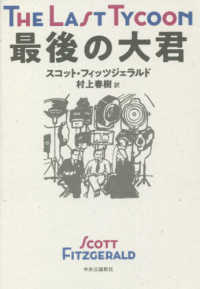内容説明
歴史教科書や一般の本で書かれている「日本の通史」を読むと「政治体制の変革は当たり前のように起こるもの」という印象を持ってしまいますが、現実には「変革を試みても様々な抵抗や思想の力が働くので社会の変革は簡単には起こらない」と言えます。本書で紹介する「政治や権力が生まれた理由」「社会での不公平の発生と変革への抵抗」「正義の必要性と思想の力」「権力の要素をめぐる力関係」などの基礎知識を駆使して歴史の流れを見ていくことで、「本来の歴史が持つダイナミックな流れ」が本当の意味で理解できると思います。
目次
第1章 教科書には書かれていない社会の基礎知識(歴史が本当に理解でき、面白いと思えるためには「基礎知識」が必要;「政治とは何か」という知識がないと学校で習う歴史が本当にわかったとは言えない ほか)
第2章 日本の政治体制の歴史を貫く一本の流れ―古代、飛鳥、奈良、平安、鎌倉時代(国家が巨大化する過程で生じる権力の不安定さと古代日本の「天皇と豪族の関係」;権力の要素としての「人事権」「権威」と、中国に対する外交姿勢について ほか)
第3章 混乱期から絶対権力の確立へと向かう時代―室町、戦国、安土桃山時代(全国支配ができる統制力がなかった室町幕府と、室町時代~戦国時代の混乱について;昔の時代に戦乱が多かったのは「コントロールされない軍事力」の暴走が頻発したため ほか)
第4章 日本に秩序をもたらした政治体制と社会システムの姿―江戸時代(時間を待つ能力を持っていた徳川家康が目指したものは「争いのない世の中を作る」こと;「大名鉢植」「征夷大将軍獲得」「豊臣家を滅ぼす決断」によって徳川家が絶対権力を握る ほか)
第5章 歴史に学ぶ」とはどういうことか(解釈に比重を置いた歴史の話に対しては「事実ではなく一つの解釈」という受け止め方を;専門研究にはない「人間心理の知識」を入れることで「より事実に近い解釈」はできる ほか)