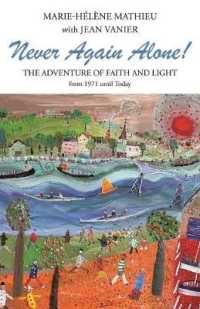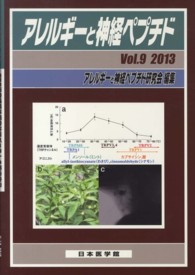内容説明
ソウル・バルセロナ両オリンピックで、いずれも4位に入賞した中山竹通は、かってさまざまに形容されていた。“本音をずばずば吐く男”“野生児”“マラソン界の異端児”…。瀬古利彦(現・ヱスビー陸上部監督)をはじめ、中山と競い合ったランナーはみな陸上の名門と呼ばれる高校、大学から実業団へと進んだいわゆるエリートぞろい。中山は信州の谷底からはい上がってきたといっていい。だからこそ十数年にわたる国内外のレースで、中山は一人闘い続けてきた。アウトサイダーの魂を抱きながら。いま中山は、指導者の道を歩みつつ、家に帰れば小学生である男の子の父親として顔を見せる。それでも、中山の反骨の炎は冷めることがない。彼の言葉と行動は、閉塞感のなかにあるといわれる今日の日本人の胸に重く響き多くの示唆を与えるであろう。
目次
大学陸上部監督(1995年~)―監督は選手の上にいるんじゃない。参考書の役割なんだ
長野(1959年~1978年)―長野の山の中から早く一人で飛び立ちたかった
不遇(1978年~1981年)―エレベーターに乗ってどん底に落ちた感じ。それで社会の仕組みが分かった
克服(1981年~1983年)―人に勝とうと思ったら、まず自分に勝たなくては
頂上(1983年~1987年)―世界一をめざした世界一のトレーニング。ダイエー時代の練習量はものすごい
誤解(1987年)―這ってでも出てくるべきだ、というのはスポーツの当たり前のルールをいっただけ
ソウル(1988年)―二位ではその上に誰かがいる。自分は世界の頂上に立ちたかった
陸連(1986年~)―なんでエリート重視と学閥、派閥なんだ。もっと中立的な立場で運営してほしい
バルセロナ(1989年~1992年)―ソウルのままで終わるんじゃ、ちょっと情けないかなと思って
訣別(1992年~1995年)―懸命に努力を重ねてきたのに処遇のひどさでむなしくなった〔ほか〕