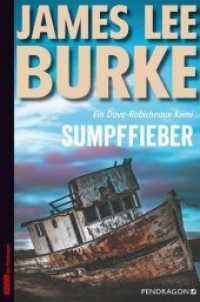内容説明
隣人愛に象徴される他者への愛が強調されてきたキリスト教の従来の見方にたいし、「甘え」の視点から聖書に光を当てて、愛されること、愛の受容がもつ深い意味を浮き彫りにし、癒されて在ることの真実の姿を示す。病める現代に贈る、甘えの大切さを語ったメッセージ。
目次
第1日 甘えの話(「甘え」という言葉;甘えの心理;なぜ欧米語には「甘え」に相当する言葉がないか ほか)
第2日 病いの話(病気とは何か;心と病気;心の病気の種類 ほか)
第3日 信仰の話(聖書と甘え;イエスと甘え;神に対する甘え ほか)
著者等紹介
土居健郎[ドイタケオ]
大正9年東京生まれ。昭和17年東京帝国大学医学部卒業。聖路加国際病院精神科医長、東京大学医学部教授、国際基督教大学教授、国立精神衛生研究所所長を歴任。著書に『精神医学と精神分析』(金子書房、1961)、『日常語の精神医学』(医学書院、1994)、『「甘え」の構造』(弘文堂、1971)、『表と裏』(弘文堂、1985)、『聖書と「甘え」』(PHP新書、1997)、『土居健郎選集』(岩波書店、2000)、『続「甘え」の構造』(弘文堂、2001)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ぼけみあん@ARIA6人娘さんが好き
4
長崎のキリスト教の大学で、甘え、病い、甘えと信仰のテーマで行なわれた3日に渡る講義をまとめたもの。著者の本は何冊も読んでいるので確認の形になった。分かりやすくまとまっているので、土居氏の甘え理論を簡単に知るには好著かも知れない。さらっと読めたが、示唆を受けた部分も幾つかある。読んでよかったと思う。2014/10/20
tuna
1
「『甘えの構造』が出る前に、甘えということを問題にした人は誰もいませんでした」とある。甘え理論が膾炙する以前以後と分けられるほどに、甘え理論の影響力が強いものだったのか疑問に思った。ともあれ、現代において「甘え」にマイナスイメージが強く付加されている(筆者自身が述べている)ことがとても重要な点だと思う。それが如何に甘え理論の読みの浅さから来ることであったとしても、問題点となるところだろう。キリスト教を引いて、主体的に「愛する」ことの強調を否定し、「愛される」体験の重要性が説かれているところが心に残った。2013/03/19
ゆりか
0
1999年の講演の書き起こし。甘えという心理は言語を介さずに生じるものなのでverbalな表現しかない西欧言語には存在しない(赤ちゃんは親をtrustする、犬は主人を愛撫する)という。感覚的、我田引水的な議論もあるが、independentを是とする西欧と対照的な日本人の特性としての甘えの指摘は感覚的に納得できる。[甘えは当たり前のものという日本人の感じ方は似たり寄ったりで、変わることはないと考えていたが、今ではマイナスイメージで受け取られることが多いのでは]という、西欧の影響からか甘え観の変化が面白い。2018/10/30