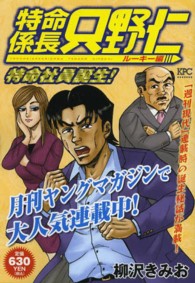出版社内容情報
利休の茶の湯とは何か。本書は、日本人の美意識の原型といえる「わびの世界」を、生活文化史の視点から明らかにする。
わび茶を大成した千利休は、下克上の世を成り上がって天下人になった豊臣秀吉に命じられて切腹する。利休が自刃にいたるその劇的な終焉は有名であるが、利休が生涯をかけて到達したわび茶の本質についてはあまり論じられることはない。利休の茶の湯とは何か、どのようにしてわび茶を確立していったのか、そして秀吉と対立するにいたったか。本書は日本人の美意識の原型といえる「わびの世界」を生活文化史の視点から明らかにする。
言葉編
?T 茶の湯のこころ
?U 人と人、物と物、人と物の出会い
?V 俗世を離れる
?W 利休の生き方
生涯編
略歴譜
千利休の生涯
内容説明
利休とは何者か。わび茶とは何か。日本人の美意識の原型を生活文化史の視点から明らかにする。
目次
言葉編(茶の湯のこころ;人と人、物と物、人と物の出会い;俗世を離れる;利休の生き方)
生涯編(略年譜;千利休の生涯)
著者等紹介
熊倉功夫[クマクライサオ]
1943年、東京都生まれ。東京教育大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。筑波大学教授、国立民族学博物館教授、総合研究大学院大学教授、財団法人林原美術館館長を歴任。静岡文化芸術大学学長、国立民族学博物館名誉教授。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
26-ring-binder
2
思想史の本は見かけるが精神史の本というのはそれよりも少ないと思っていた。本書も精神史の書籍というわけではない。しかし、千利休の精神性が初めは武家の精神性の規範になり、後年は堺の町衆を通して町人文化に引き継がれ、明治維新も耐えて現代人の精神性にまで残ったというのは感嘆する。身を糺して思考するとき、この茶の湯に源流を持つ日本人の精神性が考えを律している部分を感じると清々しい。2021/08/21
ロドニー
1
わびとは美の概念ではなく人生に対する向き合い方、態度。利休の言葉を通して改めて考える。「夏はいかにも涼しきように、冬はいかにも暖かなるように、炭は湯のわくように、茶は服のよきように、これにて秘事はすみ候。」華美な装飾を削ぎ落とされてシンプルさの中にある美しさ。豊臣秀吉とは正反対の向き合い方が皮肉でもある。秀吉が惹かれた部分でもあり、疎ましく思った部分なのではないだろうか。千利休を通してほんの少し垣間見た戦国時代とその人々、畿内随一の商人都市・堺が面白い。この時代を描く他の作品にも触れてみたい。2023/09/21
fraco
1
選ばれた言葉も素晴らしいが、その言葉を選んだ著者の解釈もまた素晴らしく、読んで心が洗われた気分になった。2017/08/19
-
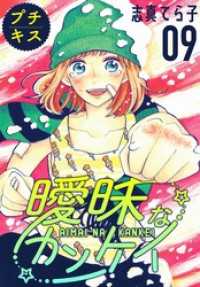
- 電子書籍
- 曖昧なカンケイ プチキス(9)
-

- 和書
- 数論講義