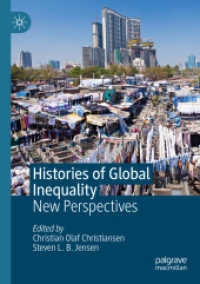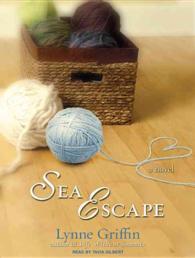- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
ブルシャスキー語、ドマーキ語、コワール語、カラーシャ語、カティ語、ドマー語、シナー語……。
文字のない小さな言語を追って、パキスタン・インドの山奥へ――。
著者は国立民族学博物館に勤務するフィールド言語学者。パキスタンとインドの山奥で、ブルシャスキー語をはじめ、話者人口の少ない七つの言語を調査している。調査は現地で協力者を探すことに始まり、谷ごとに異なる言語を聞き取り、単語や諺を集め、物語を記録するなど、その過程は地道なものである。現地の過酷な生活環境に心折れそうになりつつも、独り調査を積み重ねてきた著者が、独自のユーモアを交えつつ淡々と綴る、思索に満ちた研究の記録。
内容説明
著者は国立民族学博物館に勤務するフィールド言語学者。パキスタンとインドの山奥で、話者人口の少ない七つの言語を調査している。調査は現地で協力者を探すことに始まり、言語を聞き取り、単語や諺を集め、物語を記録するなど、その過程は地道なものである。現地の過酷な生活環境に心折れそうになりつつも、独り調査を積み重ねてきた著者が、独自のユーモアを交えつつ淡々と綴る、思索に満ちた研究の記録。
目次
0(遙かなる言葉の旅、遙かなる感覚の隔たり;表記と文字のこと)
1(フィールド言語学は何をするか;インフォーマント探し ほか)
2(好まれる「研究」と、じれったい研究;バックパッカーと研究者 ほか)
3(なくなりそうなことば;ドマー語、最後の話者 ほか)
著者等紹介
吉岡乾[ヨシオカノボル]
国立民族学博物館准教授。専門は記述言語学。博士(学術)。1979年12月、千葉県船橋市生まれ。2002年5月、東京外国語大学大学院博士課程単位取得退学。同9月に博士号取得。博士論文の題は「A Reference Grammar of Eastern Burushaski」。2014年より、現職。大学院へ進学した2003年よりブルシャスキー語の研究を開始し、その後、パキスタン北西部からインド北西部に亙る地域で、合わせて七つほどの言語を、記述的に調査・研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
読特
しゃが
あじ
サアベドラ
rosetta