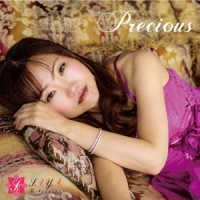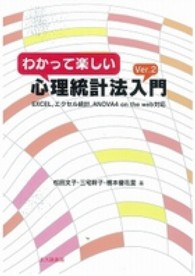出版社内容情報
【解説】
9世紀から15世紀に繁栄したアンコール帝国。「すべての道はカンボジアに通ずる」といわれた長大な王道,優れた官僚組織,巨大な石造宮殿と寺院群など,第一級の入門書。
【目次】
第1章 アンコール遺跡の発見
第2章 博物学者の時代
第3章 探検と植民地主義
第4章 探検の終わり
第5章 カンボジア王国とアンコール
第6章 アンコール、民族の誇り
資料篇 研究と保存修復
目次
第1章 アンコール遺跡の発見
第2章 博物学者の時代
第3章 探検と植民地主義
第4章 探検の終わり
第5章 カンボジア王国とアンコール
第6章 アンコール、民族の誇り
資料篇(アンコール社会と日本人訪問者;アンコールの旅;宇宙の象徴表現;年譜;アナスティローズ工法による修復;アンコール散歩;主要遺跡紹介)〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
320
私はこれまでずっと、アンコール・ワットは18世紀か19世紀のある時、フランス人の探検家が鬱蒼と茂る密林に埋もれていた遺跡を発見し、その後の調査でしだいにその全容が明らかとなり…といった発見史を信じていた。どこからそんな発想が生まれたかは明らかではないのだけれど。アンコールは既に13世紀末に周達観の『真臘風土記』なる書物に報告され、それ以降も様々な文献に登場するようである。本書は、主にそうしたアンコールの探検史と、その後の観光史を綿密に述べたもの。そうだったのか、と目を開かされることばかりだ。2017/03/03
スター
43
アンコール・ワットがどうやってヨーロッパ人に認識されてきたかについて書かれた本。2020/04/22
えふのらん
3
クメール王朝についての記述はほんの少しで、ほとんどの頁がフランスによるアンコールワットの発掘史に当てられている。といっても、そこは知の再発見双書だけあって、宗主国としてどのような影響を与えたかを自覚し、その関係の中に物語を見ているのが面白い。あまりの寂れっぷりに建造者は現地民ではなくローマ人ではないかと推測した宣教師たち、壁画を剥がし持ち帰った観光客、逆に中国への足がかりとして現地入りしたはずが、いつの間にか遺跡に魅了された軍人や欧州の美意識をかなぐり捨てて絶賛した建築家、詩人など偏見とそれをのりこえた2018/06/08
帯長襷
3
カンボジア旅行に向かう飛行機の中で読んだ。もちろん「知の再発見シリーズ」、そう簡単にインストールできる知識量ではないけれど、アンコール・ワットの発見の歴史、いや西洋的視点から「発見」と言ってはいけないことを知り、驚いた。これから現地に入る。そこで感動するであろう興奮とともにまた読み直して私的再発見を楽しみたい。2017/03/21
oputy
2
完全に復元された遺跡だと思っていたが、復元するべきところと自然に任せるところがあった。アンコール・ワットそのものの歴史についてはあまり書かれていない。2011/12/10
-

- 電子書籍
- 雪解けとアガパンサス【分冊版】 30 …