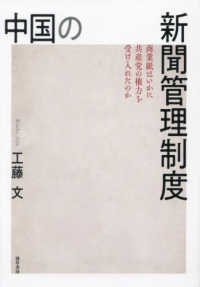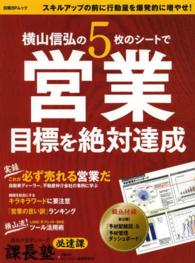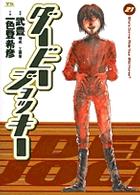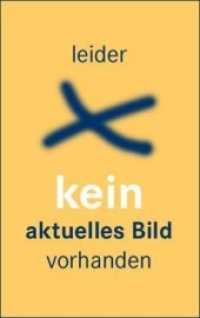出版社内容情報
<内容紹介>
日本人が古来伝承してきた源平の物語を、日本民族の無形の遺産ととらえて、著者一流の武山節でつづる。物語は保元・平治の乱から平泉まで。遺跡などのガイドは京都中心。六勝寺はじめ藤原氏の遺跡、白河天皇以来の院政関連遺跡、母常磐と牛若丸誕生にまつわる遺跡、牛若丸が預けられ、遮那王と名乗った鞍馬寺、平家の六波羅周辺の遺跡など、伝説と史実の間で遺跡をたどる。石碑などの写真、往時の地図、ガイド地図など140点。
<目次>
序 章 源氏と平氏
源氏の諸流 清和源氏の流れ 河内源氏の系譜 平氏の流れ 貴族から武士へ
第1章 京都動乱
院政とは何か 白河院政と源氏・平氏 堀河天皇と鳥羽天皇 忠盛灯篭 伊勢の瓶子 白河北殿・南殿 壮大な大 伽藍群――六勝寺跡 法勝寺跡 尊勝寺跡 最勝寺・円勝寺・成勝寺 延勝寺 院政のシンボル――鳥羽離宮 鳥羽上皇と崇徳天皇の不和 予想外の近衛天皇崩御 鳥羽離宮公園 安楽壽院 西行と観音寺 武者の世――保元の乱の意味するもの 両陣営のメンバー 内裏――高松殿跡(高松神明社) 東三条邸(三条東殿)跡 軍議 源為朝の剛勇 崇徳天皇廟 崇徳地蔵(人喰い地蔵) 信西、憎し 平治の乱、第一幕 帰ってきた清盛――平治の乱、第二幕 清盛の戦略 義朝敗走
第2章 牛若丸の旅立ち
悪源太義平、斬首頼朝の命乞いをした池禅尼 常盤御前と三人の子どもたち 牛若丸、安産祈願の地蔵尊 牛若丸産湯の井戸跡と胞衣塚 常盤御前の逃避行 常盤御前就補処 鞍馬山の牛若伝説 義経供養塔(東光坊跡) 牛若丸、息つぎの水 源義経公背比石 牛若丸の成長 牛若丸のお話 五条天神社説 御所の橋説 武蔵坊弁慶の生い立ち 金売り吉次の謎 金売り吉次の墓 首途八幡宮 全国にある吉次の墓 粟田口 蹴上~山科 牛若丸の元服 烏帽子折 血を分けた兄、阿濃禅師との対面 伊勢三郎 奥州平泉
第3章 平家にあらざるは
清盛、出生の秘密 清盛の栄達 六波羅第跡 建仁寺勅使門(矢の根門) 六波羅蜜寺 西八条第(八条亭)跡 若一神社の楠 水薬師寺、清盛の井 三十三間堂(蓮華王院) 高倉天皇と小督局 小督局の塚 祇王・祇女・仏御前 日宋貿易とその拠点 奥州の義経外伝―鬼一法眼 平氏打倒の芽 鹿ガ谷の謀議 満願寺―俊寛の面 後白河法皇との対立 文武両道の達人、源三位頼政 鵺大明神と鵺池 以仁王を奉じる 宇治橋の戦い
第4章 頼朝、立つ
伊豆の頼朝 文覚上人 挙兵 石橋山の敗戦 再起 各地で反乱 富士川の戦い 黄瀬川の対面――義経、立つ 木曾義仲の初陣 横田河原の勝利 義仲と頼朝の不和 倶利伽羅峠の戦い 「朝日将軍」と「天下一の大天狗」 四面楚歌の義仲 義仲の逆襲 頼朝、義仲追討軍を発する 宇治川の先陣争い 義仲残影 義仲寺 法観寺――義仲の首塚
第5章 義経の戦い
西海を押さえた平家 一ノ谷への道 一ノ谷西の城戸口、熊谷父子奮戦記 一ノ谷東の城戸口、梶原父子奮戦記 鵯越の逆落とし 青葉の笛 「花や今宵の」 一ノ谷のあと 後白河法皇、義経を召す 神泉苑 義経と静の出会い 義経、独断で平家追討に出発 渡辺の津― ―逆櫓の争い 屋島急襲 佐藤継信の最期 那須与一、扇の的を射る 那須与一の墓(即成院) 義経の弓流し 水軍の充実 義経、景時の先陣を拒否 壇ノ浦、決戦への覚悟 潮の流れ 波の下にも都のさぶろう―安徳天皇の最期 三種の神器 義経の八艘跳び――能登守教経の剛勇 「見るべきほどの事は見つ」―平家武将たちの最期 景清爪形観音 頼朝の戦後処理 時忠と建礼門院 宗盛、親子の別れ 大原御幸―寂光院
第6章 北帰行――義経の都落ち
梶原景時の讒言 腰越からの手紙 頼朝、義経を追い返す 梶原景時、義経の動向をさぐる 六条堀川源氏館 暗殺者か、熊野詣でか 官者(冠者)殿社 頼朝追討の宣旨 大物の浦 「義経千本桜」 佐藤忠信の最期 大津次郎 安宅の関 静、無残 平泉―藤原秀衡の死 弁慶の立ち往生 弁慶石 義経、北へ 年表
目次
序章 源氏と平氏
第1章 京都動乱
第2章 牛若丸の旅立ち
第3章 平家にあらざるは…
第4章 頼朝、立つ
第5章 義経の戦い
第6章 北帰行―義経の都落ち
著者等紹介
武山峯久[タケヤマミネヒサ]
1949年、京都市生まれ。会社勤務の傍らKBS京都アナウンススクールに学ぶ。1988年、フリー。話し方教室講師、婚礼司会、研修・講演講師、コピーライター、またパーソナリティーとしてラジオ関西「フィッシング・ステーション」「幕末ファン倶楽部」、KBS京都ラジオ「平成京都見廻隊」を企画構成し出演。「京都龍馬会」には創設とともに参加、2003年、同会のNPO法人化にも尽力、会報編集局長、枚方支部長などを兼任
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。