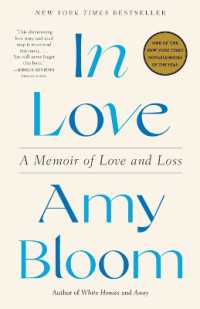出版社内容情報
これまで語られることのなかった、臨床におけるセラピストの人生の影響について語る、希有な事例集。
心理臨床とは、クライエントがセラピストと出会い、自らが抱えている問題と向き合う作業である。二人の人間が出会うことによって、臨床の場では、クライエントだけでなくセラピスト自身も大きな影響を与え、また受けることになる。本書の著者のほとんどは、いったん社会に出て活躍した後に臨床心理学を学び直し、志を立ててセラピストになった人たちで、本書は、これまで語られることのなかった臨床におけるセラピストの人生の影響について語った希有な事例集である。
はしがき──心理臨床とセラピストの人生 大村哲夫
I 子ども
第1章 非行臨床と私―ある家庭裁判所調査官の事例研究 室城隆之
第2章 警察の少年指導員から心理臨床家へ──「聞く」ということ 今井由樹子
第3章 「児童福祉」における心理臨床──児童心理司だからできることを模索して 高浪恵介
II 学校・会社
第4章 教育と心理の往還──教師が心理臨床の眼を持つとき 佐藤雅明
第5章 学生と共に歩む心理臨床──学生相談とボランティア活動 木村佐枝子
第6章 会社員から臨床心理士へ──産業臨床における葛藤とやりがい 高田俊博
III 女性
第7章 カウンセラーの存在──自分らしく生きていくために 平井理心
第8章 闇に一条の光射す──希望についての一考察 宮原亮子
第9章 さまざまな「母」との出会い──保護者面接と面接契約 酒井奈生
IV 身体
第10章 心身症と私──身体症状は魂からのメッセージ 名合雅美
第11章 小児医療と心理臨床──あらためて、そのパラダイムの相違と統合 平竹晋也
第12章 死にゆく人と出会う──在宅緩和ケアにおける心理臨床 大村哲夫
V 心理臨床と生きるということ
第13章 私の半生──心理臨床と教育と 滝口俊子
あとがき 佐藤雅明
内容説明
それぞれの人生、それぞれの道。セラピストとクライエント。別々の人生の営みが、心理臨床という場で溶け合い響き合う。クライエントだけでなく、セラピストの人生をも描き出した稀有な事例集。
目次
1 子ども(非行臨床と私―ある家庭裁判所調査官の事例研究;警察の少年補導職員から心理臨床家へ―「聞く」ということ;「児童福祉」における心理臨床―児童心理司だからできることを模索して)
2 学校・会社(教育と心理の往還―教師が心理臨床の眼を持つとき;学生と共に歩む心理臨床―学生相談とボランティア活動;会社員から臨床心理士へ―産業臨床における葛藤とやりがい)
3 女性(カウンセラーの存在―自分らしく生きていくために;闇に一条の光射す―希望についての一考察;さまざまな「母」との出会い―保護者面接と面接契約)
4 身体(心身症と私―身体症状は魂からのメッセージ;小児医療と心理臨床―あらためて、そのパラダイムの相違と統合;死にゆく人と出会う―在宅緩和ケアにおける心理臨床)
5 心理臨床と生きるということ(私の半生―心理臨床と教育と)
著者等紹介
滝口俊子[タキグチトシコ]
東京都出身。立教大学大学院文学研究科(心理学専攻)修了。臨床心理士。慶應義塾大学医学部神経科入局・立教女学院短期大学教授・京都文教大学教授・放送大学大学院教授を経て、放送大学名誉教授
大村哲夫[オオムラテツオ]
東京都出身。信州大学応用動物学及び生態学講座卒業。放送大学大学院文化科学研究科臨床心理プログラム修了、修士(学術)。東北大学大学院文学研究科人間科学専攻修了、博士(文学)。臨床心理士。民間企業を経て高等学校教員、医療法人社団爽秋会臨床心理士兼チャプレンを経て、東北大学非常勤講師、同大学院文学研究科専門研究員
佐藤雅明[サトウマサアキ]
秋田県出身。専修大学文学部国文学科卒業。埼玉大学大学院教育学研究科内地留学。放送大学大学院文化科学研究科臨床心理プログラム修了、修士(学術)。臨床心理士。埼玉県高等学校教諭(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こうきち
-
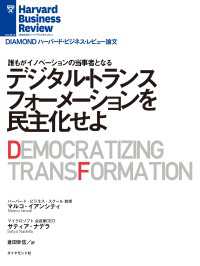
- 電子書籍
- デジタル・トランスフォーメーションを民…