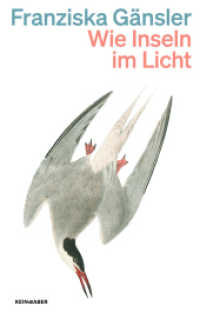出版社内容情報
児童養護施設という環境の特殊性と問題点を明らかにしながら、真に子どもたちの成長と幸せにつながるかかわり方を模索する。
児童養護施設で生活する子どもたちは、想像もつかないような困難な歴史を生きてきた存在である。そうした彼らといかにかかわっていけばよいのか。施設で暮らす子どもたち、彼らを支える職員、そして施設という環境そのものの特殊性と問題点を明らかにしながら、真に子どもたちの成長と幸せにつながるかかわり方を模索する。心理療法家として長年、施設の子どもたちと接し、その理解を深めてきた実践家による、実践家のための実質論。
目次
はじめに――子どもを見る視点の転換を
第一章 児童養護施設の生活環境の特殊性と問題点
1 個人的文化と施設の生活
2 常識という偏見
3 施設内での力関係
4 家族の文化と個人
5 自由と放任
6 家族の構成と個人文化
7 文化の葛藤
8 共同の生活と統合的価値基準
9 介入、対立、阻害
第二章 本来の家族から見た施設の家族の特殊性
1 家庭と共同生活の価値基準の置きどころ
2 家庭と施設、その関係性の違い
3 子どもと大人の非言語的なコミュニケーション
第三章 見送り、出迎えること
1 あいさつの言葉の意味すること
2 言葉のやりとりの深い意味
3 おはよう、おやすみ
4 反抗行動の器となる
5 安定と混乱および不安
6 世界の変容と子どもの安定感
第四章 きょうだいと他人
1 共同生活を営む他人と実際のきょうだい
2 血縁をどう見るか
3 協力とライバル
第五章 居室の構造上の問題
1 開放された空間と閉じられた空間
2 トイレ、風呂
3 年齢と部屋――自立のための環境
第六章 高校進学の重大な意味
1 施設での生活の継続か、施設を出るか
2 自立への希望と不安との狭間で
参考文献
おわりに
【著者紹介】
森田喜治 (もりた・よしはる)龍谷大学文学部臨床心理学科教授。臨床心理士。1956年、大阪に生まれる。大阪教育大学大学院障害児心理学課程修了後、1982年より20年間、大阪の児童養護施設で心理療法士(臨床心理士)として子どもの心理療法に携わる。施設退職後、特別顧問として施設にかかわり、被虐待児や施設で生活する子どもたちの心理療法、生活職員の指導を継続するかたわら、南大阪心理療法センターで外来クライエントのカウンセリング、スーパーヴィジョンを行い、現在に至る。また、施設の生活職員を対象とした処遇困難事例研究会の講師やエンカウンターグループのファシリテーターを行い、各地域の生活職員の指導にも当たる。著書『不登校・引きこもりの日常』(共著)ほんの森出版『家族と福祉領域の心理臨床』(共著)金子書房『体験から学ぶ心理療法の本質』(共著)創元社『パーソナリティの形成と崩壊』(共著)学術図書出版社『児童養護施設と被虐待児』創元社 など
内容説明
施設で生活する子どもたち、彼らを支える職員、そして施設という環境そのものの特殊性と問題点を明らかにしながら、真に子どもたちの成長と幸せにつながるかかわり方を模索する。心理療法家として長年、施設の子どもたちと接してその理解を深めてきた実践家による、実践家のための実質論。
目次
第1章 児童養護施設の生活環境の特殊性と問題点
第2章 本来の家族から見た施設の家族の特殊性
第3章 見送り、出迎えること
第4章 きょうだいと他人
第5章 居室の構造上の問題
第6章 高校進学の重大な意味
著者等紹介
森田喜治[モリタヨシハル]
龍谷大学文学部臨床心理学科教授。臨床心理士。1956年、大阪に生まれる。大阪教育大学大学院障害児心理学課程修了後、1982年より20年間、大阪の児童養護施設で心理療法士(臨床心理士)として子どもの心理療法に携わる。施設退職後、特別顧問として施設にかかわり、被虐待児や施設で生活する子どもたちの心理療法、生活職員の指導を継続するかたわら、南大阪心理療法センターで外来クライエントのカウンセリング、スーパーヴィジョンを行い、現在に至る。また、施設の生活職員を対象とした処遇困難事例研究会の講師やエンカウンターグループのファシリテーターを行い、各地域の生活職員の指導にも当たる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろか
田邉香織
-
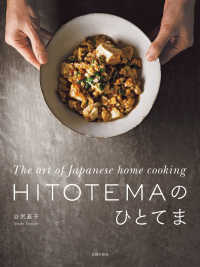
- 電子書籍
- HITOTEMAのひとてま