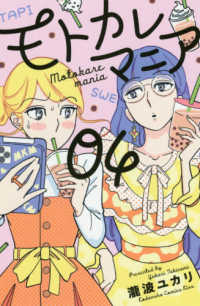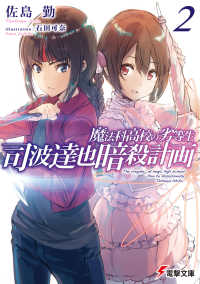内容説明
カント、ニーチェ、カフカ、ニュートンなど天才の多くは、終生、親密な人間関係をもとうとしなかった。天才にとって、創造的活動の源であった孤独は、平凡な人々の人生において、いかなる位置を占めるのかを考える。
目次
第1章 人間関係の意義
第2章 独りでいられる能力
第3章 孤独の有用性
第4章 強制的な孤独
第5章 想像力の渇望
第6章 個人の重要性
第7章 孤独と気質
第8章 分離、孤立、想像力の発達
第9章 死別、うつ病、修復
第10章 一貫性の追求
第11章 第三の時期
第12章 完全性への願望と追求
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
はなよ
14
この本を読んでいるとフロイトの学説が頻繁に出てくる。フロイトの「人間は性的に満たされていれば幸福であり、そのために人間関係を円満にしなければならない」という主張(この本ではこのように認識されている)を否定し、人間の幸福は人間関係に依存するのではなく、逆に孤独になる事で創造性を生み出し、天才を作り上げると主張する。だけど私は、その主張も極端だと思う。前にも孤独について書かれた本を読んだけど、歴史上の天才に孤独の人が多いのは事実だとしても、だからって孤独に生きている人が優秀だとは限らない。(続く2018/02/26
アレカヤシ
4
頭が腫れぼったくなった。面白く読んだけど、よく理解できていない。世界との和解、一体感は対人関係によらなくてもひとりでも可能、ということ。 (他者への愛着が人間形成にほとんど役割をはたさないような人生が、必ずしも不完全あるいは劣等というわけではない) ちょっと慰められるけど、本当にそれでいいのか?という気持ちは完全には払拭できない。カフカとヘンリージェイムズに共鳴する。 (退屈ほど大きなメランコリーの原因はなく、仕事ほどよいメランコリーの治療はない) (物事を私が望むようにではなく、あるがままに受け入れる)2017/01/02
まゆみり
1
様々な歴史上の人物を例に出して、孤独が創造的な活動に必要不可欠のものであることを示していた。今まで読んだ孤独の本と違う角度で面白かった。2015/11/16
marsnative
1
古い本を引っ張り出した。新訳の書評にもあったが、序章の「人間が独りでいるときにその人の中で進行していることは、他の人々との相互関係で起きることと同じくらい重要である。」が本書のエッセンス。個人的にはどうやらユングのいう個性化プロセスの人生半ばの移行期に踏み込んだらしい。「人生後半の課題は個人としての独自性を発見し表現すること」。死生観も含め自分を見つめ直す時期がきたようだ。しかし…他者の承認でしか自己実現ができないとしたら「孤独」さえも市場経済に組み込まれて消費されているんだろうね。うわーっ、ゾッとする!2012/01/23