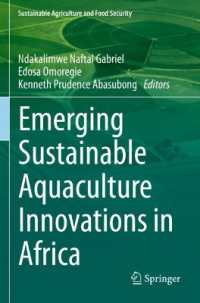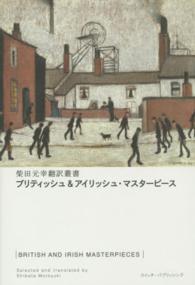内容説明
もっとわかりやすく、役に立つ災害情報をどのように伝え、どう防災に生かしていけばいいのか、それを学生も含めた多くの人に伝わる言葉で考え、結果としてこの国の防災のレベルをもう一段高いものにしてきたいと思う。私なりの視点で社会に還元できればそれに過ぎる幸せはない。この本がその議論と実践に少しでも役立てば嬉しく思う。
目次
第1章 わかりやすい情報を目指す(防災気象情報がわかりにくい;始まった防災気象情報の5段階の警戒レベル化 ほか)
第2章 災害の取材と報道(災害取材の苦い経験;災害取材とメディア対応 ほか)
第3章 最近の豪雨災害が突きつけた課題(深層崩壊に備える 紀伊半島豪雨(平成23年台風第12号)
1級河川が決壊する 平成27年9月関東・東北豪雨 ほか)
第4章 情報を生かすために(流域全体で対策を進める 流域治水;事前の対策に力を入れる 注目されるタイムライン防災)
第5章 まとめとして
著者等紹介
山〓登[ヤマザキノボル]
国士舘大学防災・救急救助総合研究所教授、静岡大学防災総合センター客員教授、人と防災未来センター上級研究員。昭和29年長野県大町市生まれ、昭和51年にNHK入局後、国内外の自然災害や防災取材を経験。平成12年、NHK解説委員(自然災害・防災担当)。平成21年、NHK解説副委員長。平成29年から現職。平成30年に兵庫県功労者表彰(防災)、防災功労者内閣総理大臣表彰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
39
182頁の地図記号、「自然災害伝承碑」。楕円形の石碑の形をイメージしてデザイン。過去の地震、津波、洪水、火山災害、土砂災害の記録を刻んだ石碑や供養塔の場所を示す。後世へのメッセージ(182頁)。2014年7月南木曽町の蛇抜けで、時間雨量が50ミリ以上。この時は70ミリで4人が流され、子ども1人が亡くなった(183頁)。確か、JRの線路も流されたため、バス代替運送だった気もする。2017年、新たな碑が建てられた。「平成じゃぬけの碑」(184頁)。2025/03/22
海燕
6
著者は元NHKで災害報道に長く携わった人。一度仕事でお目にかかったが、私のような若造相手でも高圧的でなくテレビ同様に落ち着いた口調で対応されたことが印象に残っている。本書でも過去の災害を例にとりながら、教訓や災害情報のあり方について語っている。自然災害の危険が迫りくる状況について常々思うのは、気象庁や自治体が発表する情報にどれほど工夫を重ねて改善しても、それを受け取った住民が避難行動につなげなければ役に立たないということ。「正常化の偏見」の壁は限りなく高く厚い。市民の災害リテラシーが強く求められる。2023/04/22
卓ちゃん
2
予測が難しいと言われていたが、技術の進歩により令和3年頃から線状降水帯の予測情報が気象庁から発表されるようになった。そのとき、「顕著な大雨の情報」というよく分からない名称で発表されて唖然とした。ニュースなどでは、「線状降水帯発生情報」などとして分かりやすく報道されている。災害情報は市町村や住民といったエンドユーザーにきちんと理解され、防災に生かされてこそ意味があるというのは、重い言葉だ。2024/08/28