目次
第1章 減損会計の基本的考え方・適用対象資産・処理手続の流れ
第2章 資産のグルーピング
第3章 減損の兆候の判定、減損損失の認識の要否の調査
第4章 減損損失の測定
第5章 減損処理後の会計処理・開示の取扱い
第6章 減損処理後の会計処理
第7章 ファイナンス・リース取引その他の論点
第8章 税務上の取扱いと税効果会計
第9章 適用事例の分析
著者等紹介
太田達也[オオタタツヤ]
昭和56年慶応義塾大学経済学部卒業。第一勧業銀行(現・みずほ銀行)勤務を経て、昭和63年公認会計士第2次試験合格後、太田昭和監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入所。平成4年公認会計士登録。主に上場企業の監査業務を経験した後、現在同法人のナレッジセンターにて、会計・税務・法律など幅広い分野の助言・指導を行っている。冷静かつ鋭い分析力と、実務経験に裏打ちされた的確なアドバイスは高い信頼を得ている。また、各種実務セミナー講師としても活躍中で、複雑かつ変化のめまぐるしい会計及び税実務に精通し、実践的でわかりやすい講義には定評がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
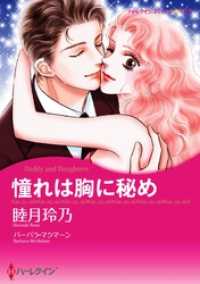
- 電子書籍
- 憧れは胸に秘め【分冊】 10巻 ハーレ…

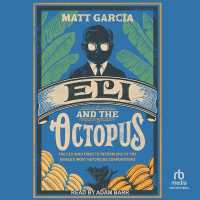

![[考論]不動産鑑定評価 - 不動産を鑑定するとは、どういうことか 桐蔭横浜大学法学部法律学科・準司法講座【不動産鑑定士】講義レ](../images/goods/ar2/web/imgdata2/49102/4910288163.jpg)



