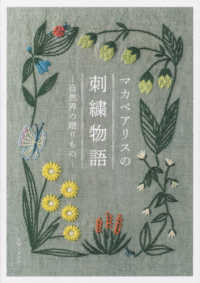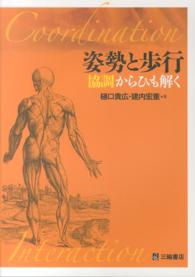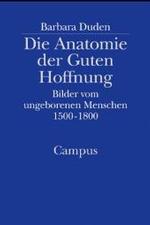出版社内容情報
気鋭の脳科学者が挑む「音楽とは何か?」。知的刺激に満ちた音楽理論書
・脳科学者が音楽のしくみ・存在意義を科学的に掘り下げる
・音楽家・音大生他、音楽を愛する全ての人に
・「音階/音律の成り立ちに関して、本書がもっとも理にかなって分かりやすい」(ピアニスト・角野隼斗氏推薦)
「音楽の仕組みや存在意義に根本から科学的にアプローチした本書は、多くの演奏家にとっても気づきの多い内容だと思う。音階/音律の成り立ちに関して沢山本を読んだが、本書がもっとも理にかなって分かりやすい。脳科学的な「緊張と弛緩」の話は、全ての時間芸術において成り立つと思う」(ピアニスト角野隼斗氏推薦文より)。 脳科学者が挑む、音楽とは何か?耳の構造から音を読み解き、なぜドレミ音階なのかを経て、音楽の誕生を考察。物理学、心理学、脳科学的視点から重層的に「音楽」を探求する流れは、知的刺激に満ちて感動的。
内容説明
なぜ、ヒトはこれほど音楽が好きなのでしょう。ヒトにとって、音楽とはいったい何でしょう。地球にヒトが誕生しなければ、音楽が生まれることはありませんでした。ヒト脳がヒト脳のために作ったものだからです。ヒトの脳があるからこそ音楽がある。この前提を胸に、音楽の正体に迫りましょう。
目次
第1章 音波と音―物理学と心理学
第2章 音の誕生―耳のしくみ
第3章 音から音階へ―聴覚心理学
第4章 ドレミの誕生―音楽心理学
第5章 音から音楽へ―音楽理論と音楽史
第6章 調性音楽の登場―和声楽
第7章 音楽のしくみ―情報理論と楽式論
第8章 音楽と脳―脳科学
第9章 音楽とは何か?―総合
著者等紹介
伊藤浩介[イトウコウスケ]
新潟大学脳研究所統合脳機能研究センター准教授。1972年生まれ。京都大学理学部卒業。同大学理学研究科(霊長類研究所)博士課程修了。博士(理学)。専門は認知脳科学、無侵襲脳機能計測学、霊長類学。ヒトや動物の知覚や認知の仕組みおよびその進化を、脳波やMRIなどの無侵襲の脳機能計測で調べている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
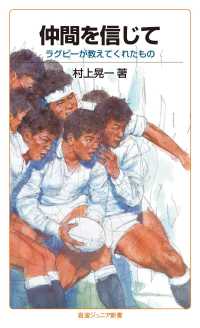
- 電子書籍
- 仲間を信じて - ラグビーが教えてくれ…