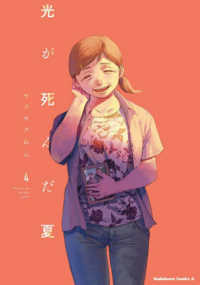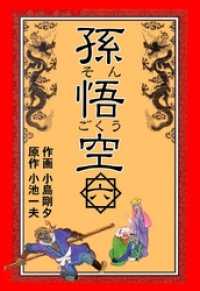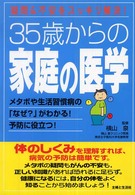出版社内容情報
人気シリーズの最新刊。身近に見られる野鳥から野山、水辺の野鳥まで、約100種の野鳥の呼び名と名前の由来を解説しています。
本書は人気の「呼び名事典」シリーズの最新刊(10巻目)です。身近に見られる野鳥から野山、水辺の野鳥まで、約100種の野鳥の呼び名と名前の由来を解説しています。ビジュアル面は既刊同様、キリヌキと生態写真を組み合わせた美しい編集で、他の図鑑類とは一線を画しています。また、著者の大橋さんは日本の野鳥写真家の第一人者であるとともに、日本の古典文学への造詣も深く、呼び名の語源・由来の解説は読み応え十分です。美しいビジュアルとおもしろい解説で、野鳥好きの方へのプレゼントにも最適です。
内容説明
身近な野鳥から野山、水辺の野鳥まで、約100種の野鳥の呼び名と語源由来、生態や識別点を解説。
目次
身近な鳥(スズメ;ハシブトガラス;ヒヨドリ;ムクドリ ほか)
野山の鳥(カッコウ;モズ;コミミズク;フクロウ ほか)
水辺の鳥(マガン;ヒシクイ;オシドリ;ヨシガモ ほか)
著者等紹介
大橋弘一[オオハシコウイチ]
野鳥写真家。1954年東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。図鑑をはじめ多くの雑誌・書籍に作品を提供するほか、テレビ・ラジオにも出演。現在、野鳥写真ライブラリー「ナチュラリー」主宰。北海道自然雑誌「faura」編集長。公益財団法人日本野鳥の会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小梅
66
野鳥の呼び名の由来がわかる。亜種が一緒に紹介されていてわかりやすい。2016/10/12
あじ
44
日本で観察できる、スタンダードな野鳥たちが主役の事典。売りは『名前の由来』が併記されていること。例えば気の毒な由来を持つ『ダイゼン(大膳)』は、宮中で食膳を司る役職・大膳職の略でありダイゼンがよく食材として用いられていた事から、名付けられたそう。また天高く翔ぶ猛禽類を、遠目でも見分けられる特徴を学べた。著者が主宰している「ナチュラリー」は、北海道の野鳥ファンにはお馴染みの出版社。野鳥に関するグッズの通販も行われている。ホームページには本書同様に、美しい写真が並んでいます。2016/10/24
seraphim
23
なぜ、その鳥が、その名前で呼ばれるようになったのか。由来を知るのも面白いと思い、読んでみた。スズメは、シュンシュン鳴くメ。メは小さな鳥を表す古い接尾語だそう。綺麗な写真と一緒に、身近な鳥が紹介されている。興味深く読んだ。2017/01/30
Hira S
4
最近、図書館特設コーナーの図鑑をランダムで借りるのだか、作者のプロフィールやあとがきが面白い。この本の写真家は文理融合について書かれている。図鑑は生息地域や確認できる季節などの科学的な情報が基本となるが、その世界の魅力を知ろうとすると、歴史や名前の由来など文系的アプローチも必要不可欠、とのこと。この道30年、16年前には脱サラしてフリーになったとのこと。頭が下がります。2021/06/19
左近
3
松原始『カラスの教科書』を夢中になって読んで以来、カラスのみならず、視界に入る生物が次から次へと気になって仕方がない。まさか、自分がバードウォッチング雑誌を定期購読する日が来ようとは。しかも、たまに書店で見かける水中生物関係の雑誌までが、おいでおいでと誘惑を…閑話休題。鳥に限らず、語源というものは、突き詰めて考えれば考えるほど、わかったようなわからないようなものになる印象があるのだが、まあ、それはそれとして、こういう本は楽しんで読めば良いと思う。最後に触れられている文理融合の大切さは、心から同意!2022/05/27