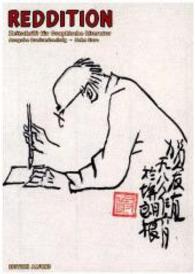出版社内容情報
樂吉左衞門が萩焼、坂倉新兵衛が樂焼に挑む、茶陶の最高峰「樂」と「萩」15代当主同士の異色コラボレーション100碗を誌上公開。
「一樂二萩三唐津」と謳われるように、樂焼と萩焼は茶陶の最高峰として数寄者から古来、好まれてきました。その現当主が自らの系譜、焼きものとしての基本を解説します。
そして……本書の見どころは、なんといっても本邦初公開!異色コラボレーションから生まれた100碗の「誌上公開」です。樂吉左衞門さんが轆轤をひねり、坂倉新兵衛さんが手で捏ねて、お互いの茶碗を焼き上げます。炎が生み出した会心の作品の数々を愛でることができるのは本書だけです。
この試みは、東京藝術大学時代からの長い友情から実現しました。樂さんが作った「萩焼」は樂の佇まい、坂倉さんの「樂焼」は萩を感じさせます。ふだんの茶碗作りとは異なる手法を通して、お互いへのリスペクト、プライドなどが垣間見える、直感的に面白い作品たちです。ぜひ、お楽しみください。
内容説明
樂と萩…。「茶陶」最高峰の基本と系譜を知る。友情が生んだ夢のコラボレーションを愉しむ。
目次
第1章 樂焼とは何か萩焼とは何か(萩焼;樂焼)
第2章 陶家十五代目同士二人友の試み(吉左衞門Xについて;学生時代の思い出と展覧会 ほか)
第3章 樂吉左衞門が「萩」そして轆轤へ挑む坂倉新兵衛の「樂」への挑戦(初めての話とこれから;「吉左衞門X新兵衛の樂吉左衞門の萩」試み ほか)
新兵衛の樂 吉左衞門の萩100碗(新兵衛「黒樂」;新兵衛「赤樂」 ほか)
著者等紹介
樂吉左衞門[ラクキチザエモン]
昭和24年(1949)‐。覚入の長男として生まれる。昭和48(1973)年東京芸術大学美術学部彫刻科卒業後、イタリア留学、覚入の没後、昭和56(1981)年十五代吉左衞門を襲名し現在に至る。当代の造形は、伝統に根ざしながらも現代性へと大きく踏み出したもの。特に「焼貫」の技法を駆使し、大胆な篦削りによる彫刻的ともいえる前衛的な作風を築き上げている。平成19(2007)年には佐川美術館(滋賀県守山市)に「樂吉左衞門館」が開館、館ならびに現代茶室を自ら設計創案した。公益財団法人樂美術館の理事長・館長
坂倉新兵衛[サカクラシンベエ]
昭和24年(1949)―山口県長門市に生まれる。昭和47(1972)年東京芸術大学美術学部彫刻科卒業、2年後に同大学院陶芸専攻修了。昭和53(1978)年十五代坂倉新兵衛を襲名し、現在に至る。昭和54(1979)年大阪高島屋襲名披露展、昭和55(1980)年ニュージーランドカンタベリー美術館寄贈(花器)、昭和59(1984)年日本工芸会正会員に(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
misui
とうこ
Kuliyama
Sentaro Urakawa