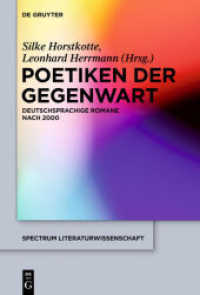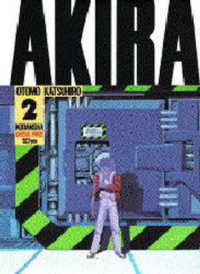出版社内容情報
鉞(まさかり)や釿(ちょうな)、槍鉋(やりがんな)などの手道具ならではの削り方を解説した書。この削り跡は、意匠的にもデザイン性の高い内装材として今や注目の的です
大鋸(おが)、前挽き(まえびき)、釿(ちょうな)、鉞(まさかり)、槍鉋(やりがんな)。古くから建築の現場で使われてきた大工道具の多くは今も現存し、さまざまな使われ方をしています。
国宝や重要文化財などの建築物を調査するとき、柱などに残された刃痕は当時使われていた刃物の種類を教えてくれます。以前は釿や斧ではつった材料をそのまま使うのは建物の見えない部分で、見える部分に使う柱などは更に鉋などで仕上げて使っていました。しかし最近は手道具ならではの刃痕を意匠的に使用し、内装材などに使うことも多くなり、手仕事ならではの贅沢な味わいが歓迎されていて、現代において、意匠性を高めるデザイン要素のひとつとして注目をあつめています。そこで、実際に使用された建築の例を紹介したり、なぐりに使用する大工道具の種類と仕立て、削り方の実践を解説しています。
■目次
絵巻から見る日本の大工道具
マサカリ(鉞)
チョウナ(釿)
ヤリガンナ(槍鉋)
伝統構法に息づく古代木工具の魅力 ー杣耕社の仕事ー
古代木工具を使った木造建築を考える
マサカリ・チョウナ・ヤリガンナを使った原木からのハツり
マサカリのハツり方
チョウナの柄を現場で挿げ替える
マサカリの柄の製作と研ぎ方
マサカリの研ぎ方
チョウナによる化粧ハツりの楽しみ方
チョウナのハツり方
ハツり作業の途中でも活躍する便利なストロッピング
チョウナの研ぎ方
チョウナの入射角について
チョウナを研ぐ際の刃の持ち方
刃返りの取り方
チョウナの柄を作る
チョウナの刃と柄の角度調整
刃沓の製作
刃沓の編み方
道具紹介
古代木工具を学ぶ
ヤリガンナの使い方と研ぎ方
ヤリガンナの使い方
節のまわりを削るときは
逆反りヤリガンナとは
ヤリガンナの研ぎ方
ヤリガンナのウラすきについて
ヤリガンナの鞘製作
匠が作るヤリガンナの魅力
チョウナとヤリガンナの魅力を考える
ヤリガンナを作る 播州三木打刃物 千代鶴貞秀
***********************************
目次
絵巻から見る日本の大工道具
伝統構法に息づく古代木工具の魅力―杣耕社の仕事
古代木工具を使った木造建築を考える
マサカリ・チョウナ・ヤリガンナを使った原木からのハツり
マサカリの柄の製作と研ぎ方
チョウナによる化粧ハツりの楽しみ方
チョウナの研ぎ方
チョウナの柄を作る
刃沓の製作
道具紹介
古代木工具を学ぶ
ヤリガンナの使い方と研ぎ方
ヤリガンナの研ぎ方
ヤリガンナの製作
匠が作るヤリガンナの魅力
チョウナとヤリガンナの魅力を考える
ヤリガンナを作る 播州三木打刃物 千代鶴貞秀
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ナディル
kaz
-
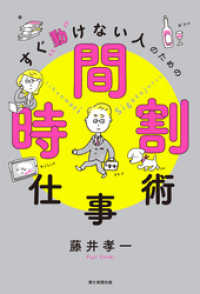
- 電子書籍
- すぐ動けない人のための時間割仕事術