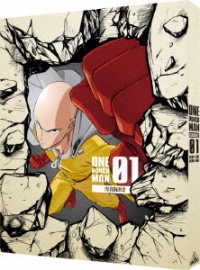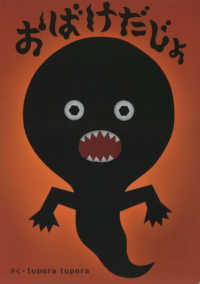内容説明
本書は、慢性の病いをかかえた患者やその家族が肉声で語る物語を中心に構成されている。今日の生物医学によって軽視されがちなこうした病いの経験、語りこそが、実は医療やケアの中心に据えられるものではないか。著者は、病いとその語りを、微小民族誌などの臨床人類学的方法を駆使しながら、社会的プロセスとして描き出そうとする。そして、病み患うことが今日どのような変容をとげつつあり、来るべき時代の医療やケアはいかにあるべきかを明らかにしようとする。本書は、この分野に関心を寄せる広範な読者に向けて書かれている。慢性の病いのケアに携わった著者の臨床知や臨床姿勢が横溢し、すでに高い評価を得ている著作の邦訳である。
目次
症状と障害の意味
病いの個人的意味と社会的意味
痛みの脆弱性と脆弱性の痛み
生きることの痛み
慢性の痛み―欲望の挫折
神経衰弱症―アメリカと中国における衰弱と疲弊
慢性の病いをもつ患者のケアにおける相反する説明モデル
大いなる願望と勝利―慢性の病いへの対処
死にいたる病い
病いのスティグマと羞恥心〔ほか〕