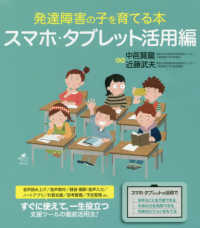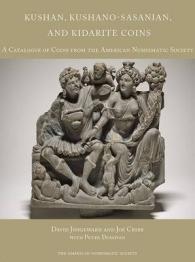出版社内容情報
カウンセラーとして著名な著者が、カウンセリングの実際場面を通して、そこに起るさまざまな問題点を摘出し解決してゆく
第1章 カウンセリングとは何か
第2章 カウンセリングの過程
第3章 心の構造
第4章 カウンセラーの態度と理論
第5章 ひとつの事例
第6章 カウンセリングの終結と評価
第7章 カウンセラーの訓練と指導
第8章 カウンセラーとクライエントの関係
第9章 カウンセラーの仕事
付章 スーパーバイザーの役割
河合 隼雄[カワイ ハヤオ]
著・文・その他
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





田舎好きひろしの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
51
【カウンセラーの多くが何か型に嵌った考えに縛られ「実際問題」の解決に戸惑っている】カウンセリングの実際場面を通して、様々な問題点を摘出し解決してゆく書。9回の「入門講座:カウンセリングの実際」講演録に加筆。1970年刊。再読。<「クライエントが家出をする時には、とめるべきでしょうか」「クライエントの質問に答えてはいけないのでしょうか」、などの質問が何度も投げかけられてくる。これらの真剣な問いに対して――たとえ、決定的な答えはないにしても――何らかの解答を与えようと思って、この講座を開くことになった>と。⇒2025/02/12
ばんだねいっぺい
27
カウンセラーの方々の苦労の一端を現実的に知ることができる本で、治療と簡単に言いがちだが一筋縄では行かないことを教えてくれる。受容は、異文化理解を伴い、共振しながら、でも、一線を引きながらが基本だが、臨機に特別な判断を迫られることは、自分の仕事とも共通するなと感じた。2018/07/01
Kano Ts
10
とても興味深く読ませていただきました。専門のカウンセラーを志す人のための本なのだろうけど、非常に平易かつ具体的に書かれているため、自分のような門外漢にとってもほとんどのパートを飽きることなく読み進めた。カウンセリングの難しさと楽しさを感じられる良い本だと思う。最近読んで印象に残っているからか、この本でも「待つこと」の重要性が説かれていたことが印象に残った。ただこの「待つこと」を適切に行うことがいかに難しく大変かということも理解できた。2024/02/14
ソーシャ
7
実際の現場でカウンセラーがぶつかる問題について、基本的な考え方から説いた河合隼雄の代表著作。カウンセリングは二律背反に耐えながら自己実現に向けて進めていくもので、時にはカウンセリングの原則を外れることも必要になるということが丁寧に説明されています。自分自身悩みながら臨床をしていることが多いのですが、「それでいいんだ」と思えたのが一番の収穫かもしれません。あと、よくなったクライエントの例として「同性愛がなくなった」があるあたりに時代を感じる…2025/03/09
エリオちゃん
4
宮本武蔵の五輪書に通じるものを感じた。 物事の基本は型を作って型にとらわれない。基礎を充分に作って柔軟に、なんだろうなぁ。2018/01/31
-
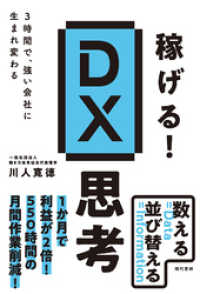
- 電子書籍
- 稼げる! DX思考
-

- DVD
- 大正野球娘。 第6巻