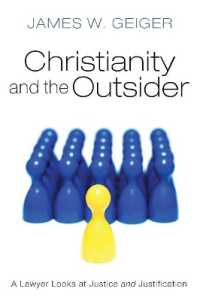出版社内容情報
病理と創造の核心にある、自分の「誕生」と「死」をめぐる問い。これを引き受けたとき、自己が再構成され、新たな生が紡がれていく
「私はどのように生まれてきたのか」
「死ぬとはどういうことなのか」
芸術が単なる癒しではなく、このような「誕生」と「死」の問いとして創造されるとき、自己を再構成していく場としてそれは機能する。このことは、描画を用いた臨床実践に何を示唆するだろうか。本書では、自由連想法を応用し、描画療法のなかで問いを活性化していく技法として「描画連想法」を提案する。
さらに、このような自己の再構成が他者や社会との関係のなかで行われることに注目しつつ、その多様性と共通性を明らかにしていく。その作業は、それぞれの仕方で「誕生」と「死」の問いを引き受けていった先人たちの、創造と病理をめぐる探究を通して行われるだろう。
序章 病理そして描画との関係における「誕生」と「死」の問い
?T 人間における2つの謎としての「生」と「死」
?U 「描くこと」と病理に関する研究の流れ
?V 本論全体の流れ
第1章 子どもにおける「誕生」と「死」の問い(1)――「描画連想法」の導入
?T 事例の考察
?U 考察
?V 出自をめぐる問いと「描画連想法」
第2章 子どもにおける「誕生」と「死」の問い(2)――「描画連想法」の実践
?T 事例提示
?U 考察
?V 主体と〈他者〉との関係をつなぐものとしての「出自」をめぐる問い
第3章 集団における「死」の経験と再生
?T 鯰絵とは何か
?U 集団的創造物としての鯰絵
?V 鯰絵の生成と主体の再構成をめぐる問題
?W 集団的創造力とは何か
第4章 躁うつ病における「生」と「死」の問い
?T 芳年の生涯・作品・病理
?U 時代の変遷・病理・創造性
?V 主体の欲望と社会の欲望
第5章 統合失調症における「死」と創造性
?T 佐伯祐三の幼年期と生涯
?U 「創造」と「病理」はいかにして結びつくのか
?V 作品に表現される主体と社会の関係性
?W 主体の構造の穴と創造性
第6章 描画・夢・症状――主体と言語との関係に注目して
?T 事例の概要
?U 事例の考察
?V 描画を治療へと導入すること
第7章 「絵解き」の技と喪の病理
?T 熊野比丘尼と絵解き
?U 『熊野勧心十界図』の構成と内容
?V 熊野比丘尼の絵解きと精神分析
?W 絵解きの空間と「他者の語らい」
第8章 「死」と創造性
?T 正岡子規の病歴
?U 正岡子規の夢(創造性)の精神分析的考察
?V 「もう一度自己を人間化すること」としての死
終章 「誕生」と「死」の問いがひらく地平へ
?T 子規の「死」から学ぶこと
?U 描画における「誕生」と「死」の問い――その多様性と共通性
?V 「描画連想法」を介して問いをひらくこと――ある女性との描画セッションを通して
?W 問い続ける主体としてあること
【著者紹介】
大西精神衛生研究所附属大西病院子ども外来
内容説明
「どのように生まれてきたのか」「死ぬとはどのようなことなのか」2つの問いは、描画を介していかに引き受けられるのか。先人たちの創造と病理から探究を進め、主体の再構成を促す「描画連想法」を臨床に導入する。
目次
序章 病理そして描画との関係における「誕生」と「死」の問い
第1章 子どもにおける「誕生」と「死」の問い(1)―「描画連想法」の導入
第2章 子どもにおける「誕生」と「死」の問い(2)―「描画連想法」の実践
第3章 集団における「死」の経験と再生
第4章 躁うつ病における「生」と「死」の問い
第5章 統合失調症における「死」と創造性
第6章 描画・夢・症状―主体と言語との関係に注目して
第7章 「絵解き」の技と喪の病理
第8章 「死」と創造性
終章 「誕生」と「死」の問いがひらく地平へ
著者等紹介
牧瀬英幹[マキセヒデモト]
2010年、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。その後、渡英し、ロンドンのラカン派精神分析組織Centre for Freudian Analysis and Researchにて、精神分析の研修を受ける。現在、大西精神衛生研究所附属大西病院勤務。専門は、精神分析、描画療法、病跡学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 奇しびなる神霊現象