出版社内容情報
現実感や共感性が育ちにくい現代の子どもに臨床家と教育者はどうアプローチできるか。現状と展望を豊富なS-HTP画を用いて解説
現実感がなく、共感性が育っていない現代の子ども。その原因は、ゲームの普及や核家族化、近所付き合いがなくなるなどで、友達や大人との関わり方が変わったことだと考えられる。そこに臨床家はどうアプローチしていくべきか。S-HTP法研究の最先端の情報を元に、S-HTP法の今後の発展や可能性について述べる。脳科学と絡めた考察や、タイの田舎・都会、日本の過去・現在の画を比較、S-HTP法の評定尺度の作成に取り組んだ研究などは、新しい視点を専門家に提供する。
第1章 描画テストに表れた子どもの心
1.最初の異変
2.1997~99年の小学生に対する調査
3.「統合性」の発達の停滞
4.S-HTPと前頭前野の機能
第2章 問題に対するS-HTPを用いたアプローチ
Part 1.タイの小学生のS-HTP画との比較
1.研究の概略
2.研究方法
3.まとめと考察
4.タイ東北部で見られた具体例
Part 2.保育園での試み――子どもの問題を保護者に伝える
1.調査の概略
2.幼児の心に影響する環境の変化
3.先生の感想
Part 3.小学校での試み――先生の関わりで1981年の絵が蘇った!
1.調査の概略
2.2年間でクラス全体の絵はどう変わったか
3.先生のどのような関わりが子どもの絵を変えたか
4.山?アクラスの一日
5.具体的な事例から
6.先生の感想
第3章 S-HTPの標準化に向けての試み
Part 1.S-HTPの評定用紙の作成と各判断基準についての研究
1.研究の概略
2.尺度による評定
3.各チェック項目の評定基準
4.S-HTP評定用紙全体に関する考察
Part 2.S-HTPにおける発達的要素・環境的要素・個人的要素の分析
1.研究の概略
2.まとめと考察
全体のまとめと今後の課題
【著者紹介】
NPO法人コミュニティ・カウンセリング・センター理事長、臨床心理士 (三上直子)
内容説明
地域のコミュニティが崩壊しつつある今、その描画も大きく変化している。現実感がない、幼い、モチーフを羅列したような絵を前に、臨床家は何ができるか。幼稚園児から大学生、そしてタイの子どもの絵を含む、180枚超の絵と共に最新の研究を紹介する。
目次
第1章 描画テストに表れた子どもの心(最初の異変;1997~99年の小学生に対する調査;「統合性」の発達の停滞;S‐HTPと前頭前野の機能)
第2章 問題に対するS‐HTPを用いたアプローチ(タイの小学生のS‐HTP画との比較;保育園での試み―子どもの問題を保護者に伝える;小学校での試み―先生の関わりで1981年の絵が蘇った!)
第3章 S‐HTPの標準化に向けての試み(S‐HTPの評定用紙の作成と各判断基準についての研究;S‐HTPにおける発達的要素・環境的要素・個人的要素の分析;全体のまとめと今後の課題)
著者等紹介
三沢直子[ミサワナオコ]
1951年生まれ。早稲田大学大学院博士課程修了、文学博士、臨床心理士。精神病院、神経科クリニック、企業の総合病院精神神経科などにおいて心理療法や心理検査に携わる一方、母親相談や母親講座をはじめとする子育て支援活動を行ってきた。現在はNPO法人コミュニティ・カウンセリング・センターや中野区子ども家庭支援センターなどで、子どもや家族の問題に関わっている職員の研修・コンサルテーションや、地域のネットワーク作りに取り組む一方、親教育支援プログラム「Nobody’s Perfect(完璧な親なんていない!)」の普及に努めている。2002年4月より2007年3月まで明治大学文学部心理社会学科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- ジョーカー(6)
-
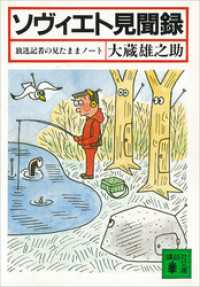
- 電子書籍
- ソヴィエト見聞録 放送記者の見たままノ…






