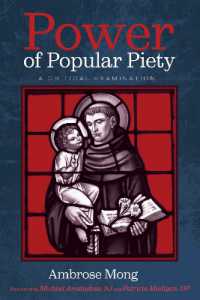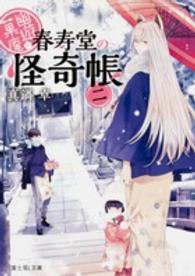出版社内容情報
アンダルシア地方の山岳地帯の麓にいまもくらす「洞窟の民」たち。
文明に疲れ、大都市の生活に疲れ、人間関係につかれた人々は、なぜ洞窟をその棲家に選び、どのように暮らしているのか。その「持たない」「ゆったりとした」「ていねいな」生き方が伝える“鬱屈”を跳ね返すヒントとは。比較文明学者である著者が、端正な日本語でつづる。
内容説明
洞窟ホテルへようこそ。暗闇に慣れたキリスト教徒。真冬の洞窟のフラメンコ。洞窟で本を読むということ…21世紀を洞窟に生きる人々の“四季暦”。現代文明の「あたりまえ」から距離を置くことで見えてきた自分を取り戻す生き方。
目次
1 洞窟暮らしの四季暦(「洞窟人」たちよ;もたない暮らしと闇の世界 ほか)
2 洞窟暮らしの歴史(動物の壁画が物語るもの―アルタミラ;始まりは坑道の廃墟だった ほか)
3 洞窟で生きるということ(シシリア島での小さな体験;持てない生活、持たない生活 ほか)
4 地平線の向こうへ―謎めいた“ジプシー”の正体を追って(ジプシーの起源;ジプシーは差別用語か ほか)
著者等紹介
太田尚樹[オオタナオキ]
1941(昭和16)年、東京生まれ。作家、東海大学名誉教授。専門は比較文明史。近年は、昭和史関連の著作も多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
雲をみるひと
39
長年にわたりスペインアンダルシア地方を訪問している作者が同地域の来歴、文化や同地区にある洞窟住宅とその住人たち、洞窟住宅の主要な利用者であるジプシーを紹介した本。取り上げられているテーマは結構マニアックだしバラバラだが、作者が好きなテーマのみを取り上げたからだからかスラスラ読める。写真が多く収録されていて現地をイメージしやすいのもよい。2021/11/03
Tenouji
14
おぉ、思ったより洞窟住居は安い!かなりの静寂らしい。圧迫感もあると思うので、向き不向きがあるようにも思うけど、一度、泊まってはみたいかな。2021/10/25
ぽけっとももんが
8
先日読んだ「どんぐり喰い」の人々は洞窟に住んでいた。日本の洞窟というとじめじめ湿気が多いけれども、こちらは年間通して室内は20度。白い壁が光を反射し、匂いも吸い込む。なかなか快適そうだ。ただ水汲みなどがたいへんだったようで、昔は井戸のある麓に持てる者が住み、ライフラインが整った現代はそれが逆転して見晴らしのいい高台に高級車が停まる。蔑称だからと使われなくなったジプシーという言葉も、じゃロマに統一すればいいのかといえばそうでもないらしい。これもまた複雑で興味深い。2022/04/16
キャリー
3
スペイン南部アンダルシア地方で洞窟に住居を構えた人たちの生活を調査したレポート。夏も冬も摂氏20度で保たれているという洞窟内は思っていたより快適そう。何より隣家との間の壁は数十メートルの厚みで静かという点は魅力的。元々は旅暮らしのジプシーの一時的な住処だったという洞窟住居、住む人が変わっても物を持たない暮らしは踏襲されているというのが不思議。室内の温度が一定で夏冬の寝具を用意する必要がないというのは大きいのかも。気候の違う日本に暮らしていると想像出来ない部分が多くて面白かった。2025/03/24
クドアンヌ
3
まぁいわゆる田舎暮らし。洞窟暮らしっていいもんだ、の「洞窟」を「海岸沿い」や「山奥」に換えても成り立つ。要は都会の早さから離れてゆっくりできる場所ならどこでもいいんだろう。スペインではそれが洞窟なだけで。ただ、車の登場で富裕層と貧困層の暮らす洞窟の場所が逆転したのは面白いなと思った。例えば道が塞がって車が使えなくなったとき、富裕層の「もたない」「ゆったり」「自由」は満たされるのだろうか。2021/12/16
-

- 電子書籍
- ”研究者失格”のわたしが阪大でいっちゃ…