出版社内容情報
巷にある「周囲に迷惑をかけないため」をメインとした終活指南のアンチテーゼとして、仏教思想家が、自由な終活を提案する。
団塊の世代が70歳まであと3年、「終活」が定着しつつある。お墓、葬式、遺言、相続などの法律や費用面をガイドした情報はすでにあるが、欠けているのは思想面、考え方の面である。巷にある「周囲に迷惑をかけないため」をメインとした終活指南のアンチテーゼとして、仏教思想家が、知的ベースを押さえながら、自由な終活を提案する。
【著者紹介】
1936年大阪府生まれ。東京大学文学部印度哲学科卒、同大学院博士課程を修了。気象大学校で二〇年間教壇に立つ。仏教を中心に宗教をわかりやすく説く。
内容説明
「迷惑かけたくない」の嘘。理想のエンディングを考えたとたん苦しくなる。―欲をかくより、本当に考えるべき「ケリのつけ方」。
目次
1章 遺言書は無用
2章 葬式は思案無用
3章 墓、墓参りはお悩み無用
4章 戒名こそ無用
5章 釈迦が教える供養とは
6章 真の終活とは何か
7章 最期を明らめてこそ生が輝く
著者等紹介
ひろさちや[ヒロサチヤ]
1936年大阪府生まれ。宗教評論家。東京大学文学部印度哲学科卒業。同大学院人文科学研究科印度哲学専攻博士課程修了。気象大学校教授を経て、大正大学客員教授。「仏教原理主義者」を名乗り、本来の仏教を伝えるべく執筆、講演活動を中心に活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shimaneko
10
不本意ながら実家の墓じまい騒動に巻き込まれちゃってるため、「お墓も戒名も法事も不要って考え方もあるんだよ」的な例として、老親に読ませようと思ったんだけど、極論すぎてダメだ、こりゃ。仏教関連のウンチクは面白かったし、お墓も戒名も要らない点では agree だけど、死者を忘れることが最上の供養だなんて、私は断じて思わない。2015/02/17
とく だま
6
日常生活をだらしなくするということでなく、昨今の宗教行事の不合理、理不尽、成り立ちを分かりやすく説く。回忌法要にしても葬祭にしても、比較的近代に寺が生活を維持するために組み立てたもので、墓も供養も葬儀も残ったものがしたければすれば良し・・しなくても良し。死の向こう側についても著者の信じることを表す。2024/12/11
ふくいち
6
まあ、そういう考え方もあるということ。大部分が私の考えとは相容れないが,その根本的原因が,死んだら浄土に行くという考え方。私も浄土宗のお寺の檀家ではあるが,神仏信じず,霊魂などないという考えだから。忘れてあげることが供養?いや,肉体も魂もないのだから,思い出の中に生きているのでいいじゃないか。葬儀は遺族の故人への思いのためにあるんだよ。お寺への批判は肯定するけど。そういう宗教的価値観の違いはともかく,遺言の作成や相続税対策を否定するなよ。生前にちゃんとしてくれていないと,相続人が苦労するぞ。2018/02/22
ヨハネス
6
死後のことばかり考えて、今現在をないがしろにすることの戒めはわかります。しかし相当辛口。死後、遺族に「自分で片づけて逝って立派だった」と思われたいのは我欲だと?そんな人ばかりじゃないと思うんだけど。「自分の葬式はするな、自分のことは忘れろ」という終活を勧めるなら結局終活するんですね。キリシタン対策として幕府が「寺で葬式をするべし」と決めたから日本人は死ぬときだけ仏教徒になるとは知らなかったけど納得しました。遺族が泣いていると死者の服が乾かないってあたしはグリム童話で読んだけど結構世界中で同じ話があるんだ。2017/08/27
葉
5
死んだ後のことを考えず、今楽しい人生を生き、家族と一緒に楽しい時間を送るのが本当の終活である。感情がたっぷり入る遺言書などいらない。葬式も望まなければやらなくてよいというお釈迦様のお墨付きである。踊りは荒御霊で仏の鎮魂をするためで、舞は鎮まって和御霊になった神を迎えるためのものらしい。貪・ジン・痴の三つの煩悩の火を弱めることが大事である。2015/10/17
-

- 電子書籍
- 大阪マダム、後宮妃になる!【単話】(7…
-
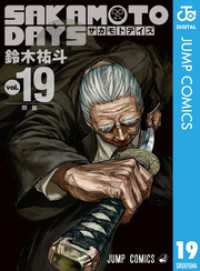
- 電子書籍
- SAKAMOTO DAYS 19 ジャ…
-

- 電子書籍
- ハイフロンティア【タテヨミ】第114話…
-

- 電子書籍
- オトナのお勉強、ハジめます。 1話 e…
-
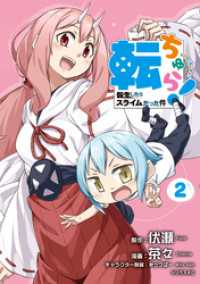
- 電子書籍
- 転ちゅら! 転生したらスライムだった件…




