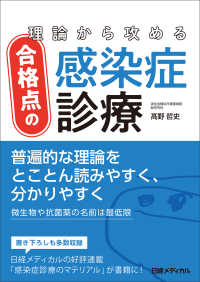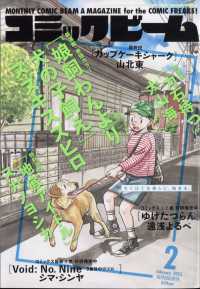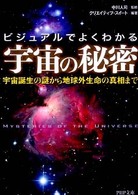内容説明
本書は、閉塞した時代に求められる人物像を、「将」と「参謀」のふたつの観点から追求した新リーダー論である。
目次
1章 将たる器とは―いかなる人間をも受け容れ、活かしきる器量はあるか(家康が見せた懐の深さ;人育ては、まず人を見ることから ほか)
2章 参謀たる器とは―将の理念を実現させる、才智の働かせ方(中間管理者としての秀吉;トップに楯つくべきとき)
3章 前例をあえて打ち破る―行き詰まりを抜け出す、将と参謀の英断とは
4章 時代の先を読みきる―世の中の変化に即応する、将たる者の視野の広げ方
著者等紹介
童門冬二[ドウモンフユジ]
1927年東京生まれ。東京都庁にて、広報室長、政策室長等を歴任後、79年に退職。以後は執筆活動に専念し、数々の話題作をあらわす。第43回芥川賞候補。歴史を題材に、現在に通じる組織と人間の問題を浮かび上がらせるという手法で、小説・ノンフィクションを問わず、多くの支持を得ている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひこうき雲
73
何のためにこの仕事をしているか、やった仕事がどれだけ組織や社会に役立ったか、それに対し組織はどう評価してくれたか。2021/08/29
Willie the Wildcat
14
リーダーシップ論の観点からは特に目新しい点は少ないが、歴史上の人物を異なる視点から振り返ることができる。印象深いのは『”象”の官位』!?思わず目を疑わずにいられなかった・・・。一方で引用した文献の記載がなかったので、自分で深堀りができないのが少し残念。以外だったのは「Hawthorne Experiments」が引用された点。心理学の授業以来(かな?)で妙に懐かしかったなぁ。2012/06/09
桂 渓位
10
加藤清正の人材登用の見方、発想が素晴らしかったです✨2019/12/01
くま
6
自分がどちらの器かはわからりません。でも、自分が望まなくても、参謀になったり将になったりすることは多々あります。天命に従える準備は必要かな?今回は島津斉彬と西郷隆盛の関係が面白かった。薩摩のカエルが世界のカエルへ。指導力がとわれるな、とただただうなずくだけ 2019/05/28
mitsu
5
過去の事例の成功・失敗を引用しながらの説明は興味深い。着眼点を拝借し、その上で自分の好きな歴史人物の伝記を読み彼らの人生を疑似体験することで、自分の身となる知識にできるのだろうなと感じた。2019/06/28