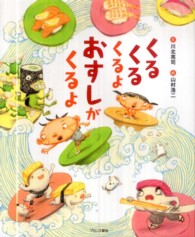- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 青春新書インテリジェンス
内容説明
名付けの漢字がこんなに変わりました―苺ちゃんや林檎ちゃん、蹴人くんが誕生した理由。
目次
第1章 暮らしの中の漢字(文字にかこまれる生活;漢字に規格がある;当用漢字の制定 ほか)
第2章 人名用漢字の変遷(人名用漢字のうつりかわり;人名用漢字はどのように決められるか)
第3章 新人名用漢字をめぐるはなし(新人名用漢字決定;新たに追加された漢字;新人名用漢字の印象 ほか)
著者等紹介
阿辻哲次[アツジテツジ]
1951年大阪府生まれ。京都大学文学部卒業、京都大学大学院文学研究科博士課程修了。京都大学大学院人間・環境学研究科教授。漢字を中心とした中国文化史を専門としている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金監禾重
4
サブタイトルから、古代以来の日本の人名の歴史やシナ朝鮮との比較などを期待したが、戦後の制度史だった。2005年刊行。「キラキラネーム」の社会問題化の雰囲気はない。縦割り行政や裁判官の不見識など問題は多々あるが、国民の要望をなるべく取り入れる姿勢や、仮名で届け出ておいて制度変更を待って解明することが許されるなど、名づけに対する思いに答える柔軟さも感じられる。2024/09/10
ま
3
面白かった。今日の戸籍係の苦悩は①日本人名の多くが表意文字である漢字を採用していること、②人名用漢字は制限列挙方式がとられ、使用できる字があらかじめ決まっているものの、字によっては俗字がある場合があること、③国民がその人名用漢字を「人名に用いたいか」と「人名に用いることを行政としてあらかじめ制限すべきであるか否か」をごっちゃにして議論してしまうこと、④人名用漢字は必ずしも常用漢字ではないことなどに由来する。特に③に関して、日本人のお上意識の強さを垣間見る気がした。2020/10/27
Y田トモコ
1
常用漢字、人名漢字がどうやって決められたか、法学部と文学部の考え方の違いなど、今まで触れたことのなかった世界をのぞいちゃった感じで、あっと言う間に読了。人名漢字の判例も面白い。使いたい漢字を認めさせるために法廷で戦う人がいるんだ、と、何だか感激してしまいましたよ。2012/05/16
結城あすか
0
「名付けの由来」とか副題にあるけど、別に個々の名前の文化的背景とかそんな物は何の関係もなく、ただただ人名漢字に関する話だけだにょ。人名漢字に含まれる、あるいは追加されたり没になったりした個々の漢字に関しての、漢字の専門家としての雑感のようなものがメインの本だにょ。パソコン等で莫大な漢字が扱える時代に漢字の制限なんてアナクロに思えるけど、著者は漢字に対して薀蓄語るのが役目の人だから、個々の漢字に人名に相応しい相応しくないのレッテル貼りをして、漢字をお上で制限するのが当然だという立場に立ってるみたいにょ。2011/05/11
小高まあな
0
意外と知らない常用漢字等についてわかりやすくまとめてあった。/探偵小説から推理小説への変遷が興味深かった2010/09/21
-
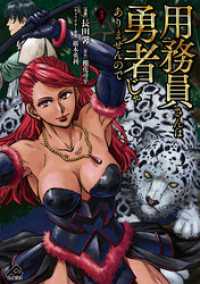
- 電子書籍
- 用務員さんは勇者じゃありませんので 3…
-
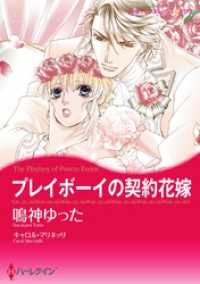
- 電子書籍
- プレイボーイの契約花嫁【分冊】 10巻…
-
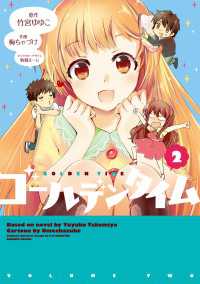
- 電子書籍
- ゴールデンタイム(2) 電撃コミックス
-
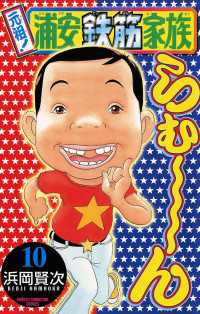
- 電子書籍
- 元祖! 浦安鉄筋家族 10 週刊少年チ…