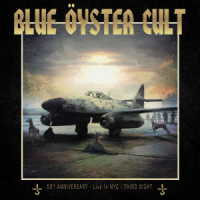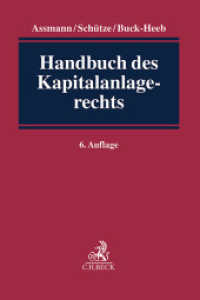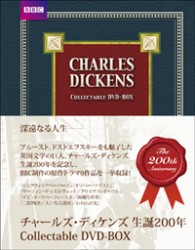内容説明
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地がなぜこの地に存在するのか、その歴史的意味とは―「エルサレム」の世界観が一目でわかる。
目次
第1章 聖書の時代
第2章 エルサレムの建設
第3章 大国の侵略
第4章 イスラムの熱風
第5章 争乱のエルサレム
第6章 聖地の現在
著者等紹介
月本昭男[ツキモトアキオ]
1948年、長野県に生まれる。1967年、新島学園高等学校卒業。1971年、東京大学文学部卒業。1980年、ドイツ・テュービンゲン大学修了(Dr.Phil.)。1981年より立教大学勤務。講義「聖書の思想」他を担当。同大学文学部キリスト教学科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みのゆかパパ@ぼちぼち読んでます
25
聖地エルサレムが歩んできた歴史を、図版なども活用して、ざっくりとたどった一冊。それなりに分かりやすくまとめられてはいたが、その歩みはそう簡単には分かったと言い切れないほどの複雑さがあり、いまなお続くパレスチナ問題の解決が容易でないことを思い知らされた感がある。迫害を受けてきたユダヤの民が安心して暮らせる土地を望む気持ちも、住み慣れた土地を奪われまいとするアラブの人たちの思いも分かるだけに、それが大国の思惑に翻弄された歴史がやるせない。願わくばその解決の道筋が平和的なものであってほしいと思わずにはおれない。2014/10/02
脳疣沼
2
いかにも分かりやすい入門書といった体裁だが、短くまとめているだけあって、意外と頭に入らない。ただ、地図が豊富なのは貴重で、他の本よりも歴史的な人々の動きが視覚的に把握しやすくなっている。しかし、地図の上であらためてイスラエルを見ると、本当に敵に包囲されており、この環境下でよくここまで、生き残れてきたなあと、平和ボケした島民の一人として感心してしまう。ユダヤ人は賢いというが、こんな環境では賢くならざるをえないだろう。2014/02/01
afuremark
1
前半は飛ばし、シオニズムあたりから復習する感じでざっと読んだ。図版を多用しているのがありがたい。長い年月に渡るユダヤへの迫害の歴史と、立国以来続くイスラエルの暴力的な振る舞い。これはギャップではなくコインの裏表だ。母国を持たず各地で差別を受け続けたユダヤの民であれば、やっと手にしたカナンの地を譲る事などできないのだろう。そして現在のユダヤによるパレスチナ人への殺戮行為に至る。 次はトンネルと分離壁を詳しく書いたものを読まないと。2014/07/20
那由田 忠
1
現代はもう少しエルサレムからみの歴史かと思ったらそうでもない。古代もエルサレムだけの歴史ということもないが、もう少し詳しいエルサレムの歴史を知りたかった。また、エルサレムの中の変化、モスクやユダヤ人街などについても知りたかったが、この程度の本に要求するのは無理だったかな。現代では、国連の2003年ロードマップについてきちんと書いてあるのはいい。新聞記事に載っているけれど、日本では知らない人が多そうだから。この点だけはブッシュが偉かった。 ハマスがテロを中止すれば、一気に解決に向かうとは思うが……2012/11/30
月見里
1
聖書のあらすじと史実のあらすじ(史実にあらすじなんて言葉を使っていいのかどうか)が比較できて地図もあって面白いなと思いながら。地理は苦手なんですが、聖書の文だけではわからない距離感がやっぱり地図見ると一見で分かるのでだいぶ歩いてるなと…創世記からシャロン政権のあたりまで簡単に読めて面白かったです。第二章がバビロン捕囚までで、三章からは個人的に目新しいことがいっぱいでした。2012/05/27
-

- 電子書籍
- 女神育成システム【タテヨミ】第32話 …