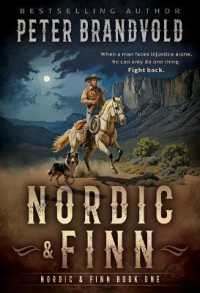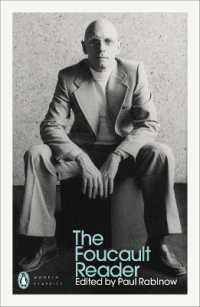目次
第1章 ゲシュタルト療法とは
第2章 ゲシュタルト療法の過程
第3章 ゲシュタルト療法の関わりと技法
第4章 ゲシュタルト療法の人格論
第5章 エンプティ・チェア技法について
第6章 事例1 “雑種の犬”に投影されたセルフ・イメージ
第7章 事例2 未完結から完結へ
第8章 事例3 「私は鶏です」
第9章 事例4 喪のワーク
第10章 ゲシュタルト派から見た身体についての小さな省察
第11章 提唱者パールズ
著者等紹介
倉戸ヨシヤ[クラトヨシヤ]
福島学院大学教授。上智大学グリーフケア研究所客員研究員。大阪市立大学名誉教授。マサチュセッツ大学大学院教育学部博士課程修了。Ed.D. San Diego Gestalt Training Center(ポルスター博士夫妻)よりDiploma取得(1978)。International Gestalt Therapy Association 理事。American Psychological Association 正会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
marcy
2
創設者フリッツ・パールズの強烈なキャラクターとメッセージを、本邦のクライエント向けに実践した例などを紹介するテキスト。具体的なやりとりが多く出てきて、親との葛藤が解消し切れていない私も合宿に参加してぜひスッキリしたい、そんな風に思いながら読んだ。ところでゲシュタルト療法はどこで受けられるのだろうか。本場のエッセンスが日本にそのまま導入できるとは全く思えないが、「◯◯◯と言ってみて」というセラピストの働きかけはあの「心屋」も使っている手法なのでは? 最近は鳴りを潜めたあの集団を図らずも思い出してビックリ。2022/03/18
デビっちん
2
再読。個の総和は全体ではなく、全体は個の総和以上の意味を持つ。部分の組み合わせを統合することで、全体の機能の観点から、初めて正しく理解される。今ここの生の体験を通して、思考、感情、行為を統合できる。ゲシュタルト心理学とアレクサンダー・テクニークの組み合わせは、とても相性が良いと教わり、実感している。何気なく選択していたことを、観察、気づきにより一度細分化し、再度統合することで、意識して選択する。体験のすべては、自分のエネルギーの表現。部分を統合できたならば、より大きなエネルギーを表現できる。2015/02/23
RNDMN
2
「今-ここ」を主軸に置き、何か未完結になっている経験を、様々な立場の「現在形の私」として置き換える事によって、経験を完結させ、実存的な意味を与え、再度人生を歩むエネルギーを生み出す過程がよく理解できた。 トランザクショナル・アナリシスとも繋がりが深い療法なのではないかと思う。 その効果や、目的、全体像が明確になったわけではないので、今後余裕があれば関連書籍も当たってみたいと思う。2014/02/15
さち
0
エンプティチェアに関心があって読んだ。エンプティチェアは未完結の体験や両極性の葛藤を扱うにはよいのだろうけど、きちんと学んでないと実践するのは怖いように感じた(その辺についてもいい書いてあったけど)。本としてはもう少し理論の説明のボリュームが欲しいのと、集団でない事例があればいいのにという感じ。あと、昔、ゲシュタルト療法の本を読んだときも思ったのだけれど、事例でセラピストがやたらと感動しているので、ちょっと辟易してしまう。。2015/07/17
デビっちん
0
ゲシュタルト療法では、人間と外界の連続に対応するために、自らも変化しなければならない。変化が見られなくなることを、パールズは4つの神経症と呼んでいる。①取り入れたものが体内で異物となって消化されていないイントロジェクション②投影したものに気づかないプロジェクション③本来は他に向かわなければならないものを反転して自分に向けるレトロフレクション④融合といわれる境界がなくなった状態のコンフルーエンス。時間を引き延ばして、無意識の連続のどこに問題があるか、自分を観察する。2014/12/23
-
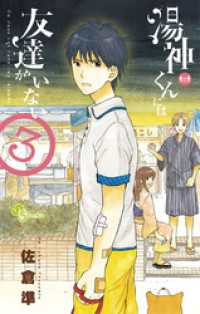
- 電子書籍
- 湯神くんには友達がいない(3) 少年サ…
-
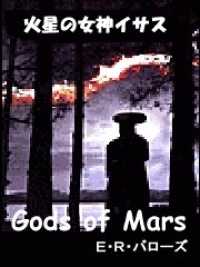
- 電子書籍
- 火星の女神イサス