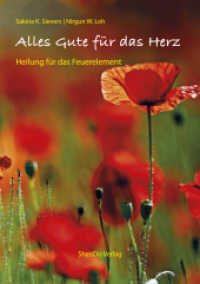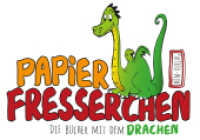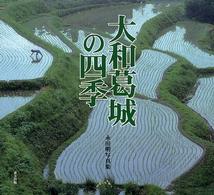内容説明
ソシュールの翻訳で知られる小林英夫の教えを受け、朝鮮語学の確立に貢献した天才言語学者、金壽卿。しかしその人生は、戦火と冷戦に翻弄され波瀾に満ちたものであった。若くして10数ヵ国語を操り、構造主義をはじめとする最新の学術に精通したその才能がたどる苦難には、20世紀のすべてが凝縮されている。知への情熱、家族との離散、社会主義体制下での制約と創造。歴史と思想がなだれ込む圧倒的評伝。
目次
第1章 植民地のポリグロット
第2章 解放と越北
第3章 リュックのなかの手帖―朝鮮戦争と離散家族
第4章 朝鮮戦争下の学問体制再編
第5章 政治と言語学
第6章 再会と復権
著者等紹介
板垣竜太[イタガキリュウタ]
1972年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科文化人類学コース・博士(学術)。現在、同志社大学社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
22
1946年 金日成綜合大学の創立メンバー。北朝鮮の言語学ひいては言語政策の中核をになった一人の言語学者の生涯をベースに、朝鮮半島の政治史、学問史、南北離散家族史を一冊に詰め込んだ意欲作。言語学に関する専門的な記述も多いので消化しにくい面もあるものの、北朝鮮における学問領域からソ連の研究業績への参照が次第に薄れ、学問の理論的正統性の根拠が金日成の言葉に置き換わっていく学問の〈主体化〉の過程は興味深いものがある。言語学から見た半島の歴史と、離散家族のエモーショナルな側面が混在して深い味わい。2022/09/13
bapaksejahtera
11
京城帝大出身の語学の天才、その後北に渡り朝鮮語学者として活動した金壽卿(キム スギョン)の評伝であると共に、特に北におけるスターリン影響等の言語政策史に触れる。ハングルの成立が朝鮮語漢字音の矯正にあった事、中国音韻学やモンゴル文字との関連を避けぬ記述、ハングルという呼称を初めて唱えた20C初の周時経、近代における綴字法(論)の変遷等面白い。結果的だが綴字形態主義の尊重という点では北の綴字法が好ましいとも思う。著者は日本社会の北朝鮮への偏見を批判するが、北の人権問題無視等政治的偏向が私の読書の妨げになった 2022/10/31
t0t0165
1
ある知識人のライフヒストリーから描かれる東アジアの20世紀史。植民地支配、南北分断、国家建設という大文字の出来事の中で、研究者として、家族を持つ一個人として時に能動的、時に受動的に選択と実践を迫られる。言語学者として残した彼の業績については、不学ゆえに理解が追いついていないが、それでも圧倒的な語学力を駆使して論理的に説得力を持ってハングルのあり方を探究したことはうかがえる。2022/05/10