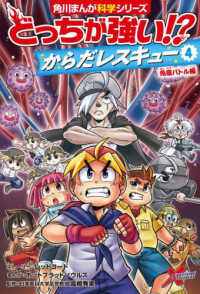内容説明
教室での礼、貰い物への返礼など、日本社会に溢れる「礼」。それは古代中国に生まれた、世界を律するための概念であり、今日まで広く深く日本の文化と歴史を規定している。しかし、「礼」とは一体何か、歴史学的に解明し本質を捉える議論はこれまでにされてこなかった。気鋭の日本中世史研究者が中国古代思想に分け入り、「礼」の根源に迫る画期的力作。
目次
プロローグ―“礼儀正しい日本人”が“礼”を知らない落とし穴
『礼記』と“礼”思想―人間関係の根底としての敬譲
“礼”のメカニズム―相互作用・外形・理性
“礼”の類別機能―人を禽獣と分ける秩序の大前提
社会の持続可能性を保証する冠昏喪祭―先後絶対主義と根源至上主義
世界の原点・万物の始原としての「天」―“礼”の絶対性を保証するもの
戦争で敵を討つ“礼”―軍礼と時機最適主義
射(弓術)と宴会の“礼”―祭祀と秩序の維持管理
“礼”と“楽”―外と内から立体的に統治する術
“礼”と外交・内政―立場最適主義と職分忠実主義
君子の成績簿・『春秋左氏伝』―万人を役割に縛る“礼”
エピローグ―“礼”とは何か
著者等紹介
桃崎有一郎[モモサキユウイチロウ]
1978年、東京都生まれ。2001年、慶應義塾大学文学部卒業。2007年、慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学、博士(史学)。現在、高千穂大学商学部教授。専門は、古代・中世の礼制と法制・政治の関係史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
10
門外漢による中国古代の「礼」入門ということで恐る恐る手を付けたが、日本史研究者の視点による、『礼記』『左伝』の記述を利用した「礼」の整理・学習ノートといった趣きで、「礼」とはどういうものかがよく整理されている。細々とした問題点がないわけでもないが、質的に有象無象の『論語』本などとは一線を画している。本書の中身がどうというよりも、これを基礎として著者が今後どういう研究をされていくのかが重要。2020/08/14
Tom
4
2020年刊。著者の『武士の起源を解きあかす』内で《礼》に言及している箇所が何個かあり、気になった。《礼》とは中国伝来の思想であり、我が国における《礼》の受容は遣唐使廃止までに済んでいるので、よって唐代までに成立した《礼》が基礎となっている、というところから出発する。儒教の思想である《礼》の経典は「四書五経」のひとつの『礼記』である。余談だが、「四書」は初学者向けとして十二世紀以降に追加されたもので、本来は「五経」である。『礼記』は周王朝時代を理想とし、その思想と実践の書である。→2023/11/01
Go Extreme
1
『礼記』と《礼》思想─人間関係の根底 《礼》のメカニズム─相互作用・外形・理性 《礼》の類別機能─人を禽獣と分ける秩序 社会の持続可能性(サステイナビリティ)を保証する冠昏喪祭─先後絶対主義と根源至上主義 世界の原点・万物の始原としての「天」─《礼》の絶対性を保証するもの 戦争で敵を討つ《礼》─軍礼と時機最適主義 射(弓術)と宴会の《礼》─祭祀と秩序の維持管理 《礼》と《楽》─外と内から立体的に統治する術 《礼》と外交・内政─立場最適主義と職分忠実主義 君子の成績簿・『春秋左氏伝』─万人を役割に縛る《礼》2022/01/22
-
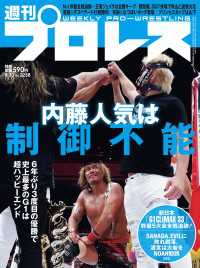
- 電子書籍
- 週刊プロレス 2023年 8/30号 …