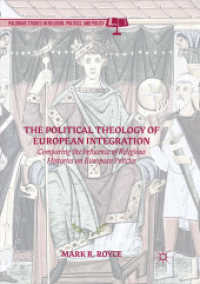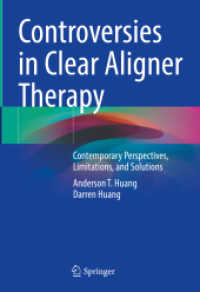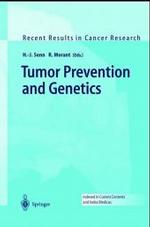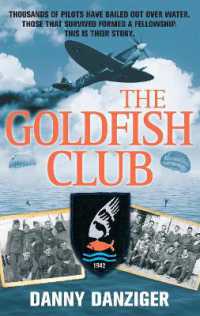- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 歴史
- > 辞典・事典・年表・資料
内容説明
本書は明治二十年代を舞台に、御料地の設置から払い下げなどの「処分」までを、膨大な一次史料をもとに詳細に分析、通覧する。その中心になるのは、長州勤王の志士として活動し、維新後は官僚、政治家となった品川弥二郎。これまで光のあたらなかった明治の「もうひとつの政治」を初めて明らかにする、画期的研究。
目次
第1部 明治二〇年代の御料地認識形成条件(「皇室財産設定論」に見る御料地認識;品川弥二郎と明治一七、八年の「宿志」)
第2部 明治二〇年代の御料地「処分」(御料鉱山の払下げ―御料地と鉱工業政策・財政政策;御料地事業拡大の法制度的根拠―明治二四年の「皇室会計法」制定;静岡支庁管下御料林「処分」をめぐる諸問題―御料林と製糸業奨励政策;北海道御料林除却一件―御料地と国土保全政策)
明治立憲制の中の皇室財産
著者等紹介
池田さなえ[イケダサナエ]
1988年生。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。京都大学博士(文学)。現在、京都大学人文科学研究所助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
7
「皇室財政の研究」きっかけ。品川弥二郎という政治家を狂言回しに明治20年代の皇室財産を巡る歴史を語る本。宮中、つまり皇室と宮内省に対して府中、内閣は別、という旧憲法の仕切りの元、終戦まで秘匿された宮中の財源で政治家達が裏金を作ったり、冒険的な事業運営をに暴走したりという話。ただし、「伊藤や松方、山縣らは、議会政治が始まって以降の不安定な政権を重要な局面において助ける目的で天皇との関係を築き、宮中との関係を円滑化して政治資金の引き出しを図った」p412と言う方向の話しはほとんど無いのが残念。2024/12/13
秋津
3
凄い。皇室財産のうち不動産である「御料地」を取り上げ、単に皇室の財源(収益)としてではなく、殖産・地方自治の基盤強化といった行政上の課題解決、また、御料局長であった品川弥二郎が携わった鉱山払下げの事例に見られるような、政敵の政治資源拡大阻止への利用など、「モノ」としての御料地が持つ様々な政治的な意義を明らかにしている。御料地とそれを巡る制度やアクターの活動、そして「宮中・府中」関係を考える上で、本書は大きな意義を持つと感じた。2019/06/29
takao
0
ふむ2025/08/04
-
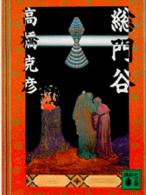
- 和書
- 総門谷 講談社文庫