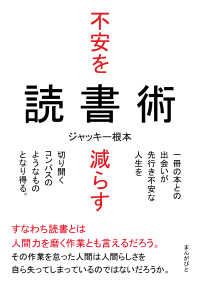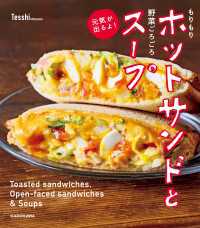出版社内容情報
初詣や命名の習慣、戸籍制度、身体測定、体操など生活の中に確かな痕跡を残す日本の植民地主義…第一線の研究者による論集。
内容説明
天皇制と近代化・文明化、同化と差異化の狭間でゆれる「日本型植民地主義」の姿を、生活レベルからとらえる。
目次
序論―日本の植民地主義を考える(水野直樹)
朝鮮人の名前と植民地支配(水野直樹)
植民地支配、身体規律、「健康」(鄭根埴)
植民地における神社参拝(駒込武)
台湾先住民と日本語教育―阿里山ツオウ族の戦前・戦後(松田吉郎)
著者等紹介
水野直樹[ミズノナオキ]
京都大学人文科学研究所教授。1950年京都生まれ。京都大学文学研究科(現代史学)博士課程修了。1985年より京都橘女子大学を経て、91年京都大学人文科学研究所助教授、2001年より現職。専攻は、朝鮮近現代史・東アジア関係史。日本の植民地支配、特に「人の支配」にかかわる諸問題や朝鮮における治安維持法体制の問題を研究している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kotsarf8
3
京大での集中講義が元になった一冊。某k大新聞でお世話になった先生方も関わってらっしゃいます。まず、植民地主義とはなにか、そして日本が第二次世界大戦以前に行った植民地主義の特徴(同化と排除、天皇制)の概説をしたのち、①朝鮮半島での姓名、②同じく朝鮮半島の健康政策、③台湾のある私立学校を舞台にした神社参拝問題、④台湾先住民の日本語教育という、具体的なテーマに即して、日本の植民地主義が現地住民の「生活」にいかなる影響を与えたのかを考察します。 日本の植民地主義について知りたい人には、なかなか手頃な入門書になる2012/12/09