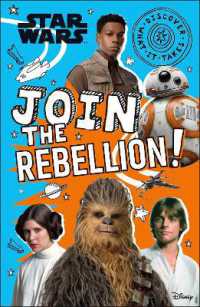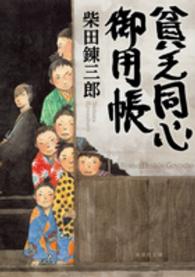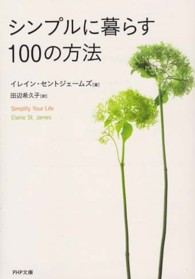内容説明
ラカン自身により「私を読むことのできる少なくとも一人の人物」と評され、ラカン派の領袖として活躍する精神分析家ミレールの初めての入門書。哲学と精神分析、臨床、政治などのテーマのもと、その思想がコンパクトに論じられる。ラカンとともに、そしてラカンを超えて独自の歩みをみせる、現代ラカン派の良質な見取り図となる一冊。
目次
序(言葉を愛する者;解明への情熱 ほか)
第1章 哲学から精神分析へ(サルトルの読解者としてのミレール;ルイ・アルチュセールからジャック・ラカンへ ほか)
第2章 精神分析臨床(分析経験;精神分析、心理学と精神医学 ほか)
第3章 ラカン的政治(毛沢東主義から政治の懐疑論へ;精神分析の倫理 ほか)
第4章 現実界に向かって(精神分析のパラダイムの変化;意味と現実界を分けること ほか)
著者等紹介
フルリー,ニコラ[フルリー,ニコラ] [Floury,Nicolas]
1978年生まれ。パリ第10大学にて、臨床心理士の資格と哲学の博士号を取得。現在は哲学と精神分析の関係についての研究に取り組んでいる
松本卓也[マツモトタクヤ]
1983年高知県生まれ。高知大学医学部卒業、自治医科大学大学院医学研究科修了。博士(医学)。専門は精神病理学。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bevel
5
ミレールはラカンを「明解な著作」へ再構成した。まずミレールは、ラカンと構造主義を両立可能にする基礎付けを行い、空白の升目を移動するパズルゲームとして主体をモデル化する。そして「シニフィアンが他のシニフィアンに対して主体を表象する」とは真理の自律理論(=整合説)を鏡像理論(=対応説)の用語で書き換えるものと見なす。しかし、ミレールはその後、この哲学的読解を捨て、文脈ないし特異性を扱う精神分析家になる。享楽は症状と結びつく言葉で、ファンタスムと対比されるなど、ラカン派の基礎的な言葉遣いが学べる点でもよいと思う2023/02/18
ルンブマ
3
ミレールの約120本の論文のうち、主要13本を年代順にまとめてラカンから引き継がれたミレールの思想をまとめた本。この『現実界に向かって』の訳出のおかげで、近年の(2014年の)ミレールの発表(「無意識と語る身体」)で語られた内容がものすごくクリアに理解できるようになった(症状の形式的外皮とファンタスムの論理)。なるほど、それがそうなって例の「脚立」概念に繋がるのかぁ、と。松本卓也さんにマジで感謝。2020/09/20
しんだもずく
1
ラカンの正統後継者でありながら本邦では需要の少ないミレールの入門書。ラカンの諸著作にサルトルを見、構造主義思想家としてラカン理論を体系化した哲学者としての初期のミレールの仕事から、「ラカンには一切の教義は(言語で構築された無意識というテーゼさえ)存在しない」とまで言うようになった精神分析家としてのミレールまで、その思想の変遷をバランス感覚良くまとめていて非常によい。一般に扱いづらいとされる後期ラカンをどのように捉えたのか、またそれをどのように発展させて行ったのかというところまで丁寧にまとまっていて助かる2021/10/21
🍕
1
反哲学としての精神分析の可能性を探る本として読めた2020/10/18
シン
0
最終章が面白かった2025/02/04