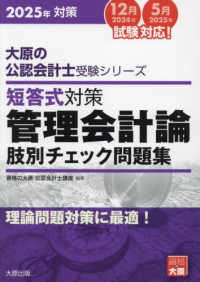出版社内容情報
精神分析が導く現代資本主義社会の突破口 精神分析が導く現代資本主義社会の突破口?
ジャック・ラカンが提出した「剰余享楽」「資本主義のディスクール」といった概念は、現代社会の現象の把握のためにきわめて有効だ。本書では力強く展開する現代ラカン派の理論を紹介するとともに、うつ、自閉症、ヘイトスピーチといった、臨床や政治社会における広範な事象に応用し分析を試みる。精神分析の言説に新たな息吹をもたらす、ラカン派の俊英による鮮やかな社会論。
「こうして、「不可能な享楽」は「エンジョイ」になり、〈父〉はデータの番人になった。現代の私たちは、後者による徹底的な制御のもとで、前者の「エンジョイ」としての享楽の過剰な強制――「享楽せよ! Jouis !」という超自我の命令――によって、そして、その結果として消費されるさまざまなガジェットがもたらす依存症的な享楽によって慰められながら、徐々に窒息させられつつあるのではないだろうか。だとすれば、そこから抜け出すことはいかにして可能なのだろうか?」(本書より)
まえがき
1 ラカン派にとって現代とはなにか?
2 本書の構成
第?部 理論
第一章 現代ラカン派の見取り図
――ジャック=アラン・ミレールの議論を中心に
1 近代精神医学から精神分析へ
2 象徴界の衰退と〈父〉の複数化
3 臨床形態の問いなおし――普通精神病と自閉症
4 セクシュアリティの変化――「露出」と「依存症」
5 症状からサントームへ
6 無意識から遠く離れて――無意識と話存在
7 脚立――昇華の新しいパラダイム
8 男性側の式から女性側の式へ
第二章 4(+1)つのディスクールについて
――マルクスから資本主義のディスクールへ
1 ディスクールとはなにか?
2 剰余価値と剰余享楽
3 剰余享楽の袋小路――「六八年五月」と対峙するラカン
4 四つのディスクール
5 資本主義のディスクール
6 現代の「うつ」と資本主義のディスクール
第三章 性別化の式について
――キルケゴールはいかにして男性側の式のリミットを越えたのか?
1 キルケゴールの愛は宮廷愛だったのか?
2 〈物〉とシニフィアン、そして不安
3 ふたたび『アンコール』へ
4 『愛のわざ』のラカン的読解
5 例外を空想するのではなく、例外になること
第?部 臨床
第四章 DSMは何を排除したのか?
――ラカン派精神分析と科学
1 「意図せざる結果」
2 DSMによる神経症の消滅
3 主体を排除するものとしての「科学」
4 現代精神医学の彼岸
第五章 現代の病としての「うつ」
――「現勢神経症」と資本主義のディスクール
1 デプレッションとメランコリーをめぐる精神医学史
2 フロイトにおけるデプレッションとメランコリー
3 神経衰弱/現勢神経症の復権
4 欲動の処理不全と「資本主義のディスクール」
5 デプレッションの神学??ラカンのデプレッション論
6 デプレッションの表象文化論?
7 現勢神経症の復権に向けて
第六章 「恥の死滅」としての現代
――羞恥の構造を読む
1 「恥」と眼差し
2 視線と羞恥の構造
3 対人恐怖
4 窃視症
5 露出症
6 眼差しのラカン的存在論――存在論は「恥在論」である
7 現代における「恥の死滅」
第七章 自閉症をめぐるフランス的問題
1 時代遅れの精神分析?
2 「壁」についての反応と「精神分析禁止法案」
3 ラカン派の自閉症研究
第?部 政治
第八章 レイシズム2・0?
――現代ラカン派の集団心理学1
1 ヘイトスピーチのめざめ
2 二つのレイシズム論
3 フロイトの症状
4 「集団心理学」を再考する
5 レイシズムにおける〈父〉と享楽の病理
6 精神分析はレイシズムに対して何ができるのか
第九章 享楽の政治
――現代ラカン派の集団心理学2
1 「享楽の政治」について
2 「法は法である」――象徴界のフラットな使用に潜む享楽
3 集団的同一化における享楽の動員
4 〈父の名〉の秩序から「鉄の秩序」へ
第一○章 ラカン的政治のために
1 否認の主体とシニシズム的空想
2 シニシズムを横断する
3 大文字の「否」から肯定性へ
4 ラカンと政治理論
5 大学のディスクールから分析家のディスクールへ
あとがき
参考文献
松本 卓也[マツモトタクヤ]
著・文・その他
内容説明
ジャック・ラカンが提出した「剰余享楽」「資本主義のディスクール」といった概念は、現代社会の現象の把握にきわめて有効だ。本書では力強く展開する現代ラカン派の理論を紹介するとともに、うつ、自閉症、ヘイトスピーチといった、臨床や政治社会における広範な事象に応用し分析を試みる。精神分析の言説に新たな息吹をもたらす、ラカン派の俊英による鮮やかな社会論。
目次
第1部 理論(現代ラカン派の見取り図―ジャック=アラン・ミレールの議論を中心に;4(+1)つのディスクールについて―マルクスから資本主義のディスクールへ
性別化の式について―キルケゴールはいかにして男性側の式のリミットを超えたのか?)
第2部 臨床(DSMは何を排除したのか?―ラカン派精神分析と科学;現代の病としての「うつ」―「現勢神経症」と資本主義のディスクール;「恥の死滅」としての現代―羞恥の構造を読む;自閉症をめぐるフランス的問題)
第3部 政治(レイシズム2.0?―現代ラカン派の集団心理学1;享楽の政治―現代ラカン派の集団心理学2;ラカン的政治のために)
著者等紹介
松本卓也[マツモトタクヤ]
1983年高知県生まれ。高知大学医学部卒業、自治医科大学大学院医学研究科修了。博士(医学)。専門は精神病理学。京都大学大学院人間・環境学研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
シッダ@涅槃
またの名
ひばりん
しゅん
-

- 和書
- 後拾遺和歌集攷