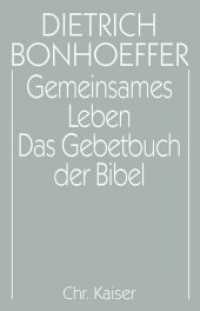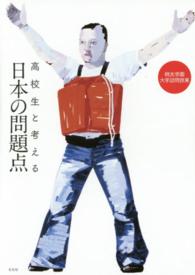出版社内容情報
手仕事をめぐる言説に隠されたジェンダー構造を明らかにする画期的研究 手仕事をめぐる言説に隠されたジェンダー構造を明らかにする画期的研究。人々の関心を集めながらも、社会の傍流へ追いやられる手仕事がある。そんな「やりがいのあるものづくり」が奨励されるとき、その言説にはジェンダーの問題が潜んでいるのではないか。学校での家庭科、戦時下における針仕事の動員、戦後の手芸ブーム、伝統工芸における女性職人、刑務所での工芸品作りなど、趣味以上・労働未満の創作活動を支えている、フェミナイズ(女性化)する言説を探る。 序 言説の旅の始まり 山崎明子[ヤマザキアキコ]
人々の関心を集めながらも、社会の傍流へ追いやられる手仕事がある。そんな「やりがいのあるものづくり」が奨励されるとき、その言説にはジェンダーの問題が潜んでいるのではないか。学校での家庭科、戦時下における針仕事の動員、戦後の手芸ブーム、伝統工芸における女性職人、刑務所での工芸品作りなど、趣味以上・労働未満の創作活動を支えている、フェミナイズ(女性化)する言説を探る。
「多くの女性化された創造活動は、それが「仕事」であっても、「家庭」と結びつけられやすく、またその語りは「楽しさ」や「やりがい」など、自己啓発的な言葉に満ちている。そして女性化された仕事は、今日、グローバルに組織されたものづくりの現場に広がっている。そこには、「女性」だけでなく、移民、女性化された男性、そしてその子どもたちも含まれ、家父長的な家族観がまだ強く、労働のための法やその準備のための教育が十分に確立していない社会では、こうした家父長的な構造を容易に利用できてしまうのだ。近代家族の中で女性たちが行ってきた仕事は、より女性化された人々に移譲され、消費者となった女性たちには移譲の現実が不可視化されている。この問題は、今を生きる私たちにとって、決して他人事ではないはずだ。」(本書より)
◎目次
序 言説の旅の始まり
言説が生み出すものづくりの世界
梅棹忠夫かく語りき
ジェンダー化のポリティクス
本書の構成
第一章 万一のために手芸をせよ――近代手芸論
学校で手芸を学ぶべし
皇后だって養蚕をしているのだから……
先ず心の美より養ふべし
母たる方々に手芸は実に必要
手工は家庭をして平和幸福の天地とならしむ
申さば一の慰み稽古の如くなり
第二章 国益に供せよ――内職論
産なきの輩への内職のススメ
国益に供せよ
誰にでもできて上品
決戦下の主婦の務でありませう
お金もうけだけが目的でできるものではありません
第三章 貴女は慰めになる――戦時下の手芸論
戦争中なのに手芸なんて
軍艦だつてもとは手芸から出発してゐる
花をつくっている奴は非国民だ
真心の弾丸
メディアの中の慰問人形
背?に小さな人形をぶら下げて
戦時だからこそ手芸が必要なのです内容説明
目次
第1章 万一のために手芸をせよ―近代手芸論
第2章 国益に供せよ―内職論
第3章 貴女は慰めになる―戦時下の手芸論
第4章 祈りを届けよ―千人針の表象
第5章 家庭は貴女の展覧会場―戦後手芸論
第6章 救世主は貴女だ―女職人論
第7章 社会の役に立たねば―刑務所の伝統工芸論
終章 言説のゆくえ著者等紹介
1967年、京都府生まれ。千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。現在、奈良女子大学生活環境科学系教授。視覚文化論、美術制度史、ジェンダー論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みなみ
ちり
aof
takao
-

- 電子書籍
- GO ANd GO 22 月刊少年チャ…