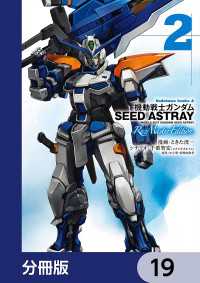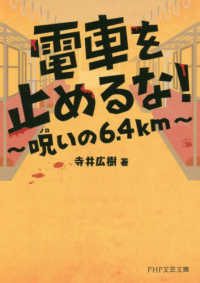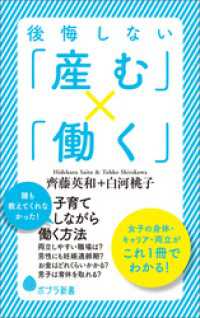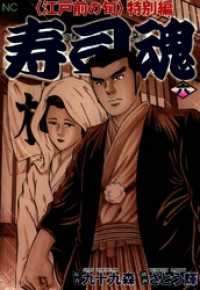内容説明
老いとか何か。老いは不意に我々を捉える。何人もこの人生の失墜をまぬがれることはできない。老いという人生の最後の時期に我々はいかなる者となるのか?この人間存在の真の意味を示す老いの生物学的、歴史的、哲学的、社会的、その他あらゆる角度からの、徹底的考察!!畢生の大作『第二の性』と双壁をなす問題の書。
目次
第1部 外部からの視点(生物学からみた老い;未開社会における老い;歴史社会における老い;現代社会における老い)
著者等紹介
ボーヴォワール,シモーヌ・ド[ボーヴォワール,シモーヌド] [Beauvoir,Simone de]
1908年1月9日パリ生まれ。1926年家族の反対を押し切ってソルボンヌ大学哲学科に身を置いた。そこで“事実上の”夫となるサルトルと出会う。1943年に最初の小説『招かれた女』を発表、サルトルと並び実存主義作家の代表として機関紙『レ・タン・モデルヌ』で活躍した。その後1949年に代表作となる『第二の性』で一躍注目を浴び、現代フェミニズム運動の先駆けを担うとともに、1954年、『レ・マンダラン』でゴンクール賞を受賞し、フランス文壇の第一線で活躍を続けた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
102
ボーヴォワール62歳1970年の著作。"いつまでも気持ちは若い"ということは、若いということに価値を置いている裏返しであることに気付かされる。死を意識する事はあっても、老いは直視しないまま時を過ごしがちであり、誰にでもいつの間にか訪れるもの。上巻では外部からの視点として、生物学的に、また社会的な老いの歴史を膨大な資料からフォーカスしている。この時代にすでに退職後の年金と孤独についての言及があり、今とほとんど変わらないことに驚く。多くの文学作品も引用されており「楢山節考」も考察されていた。リア王も読みたい。2021/07/12
ehirano1
82
何とも切なくなるというか残酷というか・・・しかしこれが現実ですね。そうであるなら足掻こうとはせずに老化を素直に少しずつでいいので受け入れていくしかないと思いました。しかしそうするには幾らかの工夫と技術が必要のようです。まあ、これが認識できただけでも僥倖でした。2024/06/25
榊原 香織
81
人生の曲がり角にはいつもボーヴォワールがいる なんちって。 高校生の時に”第2の性”を読み、今はこれw 文化人類学的に、少数民族の老人の扱い、記述してるんだけど、ちょっとどーかと。 アイヌ民族からクレーム来そう。 日本の事例も違和感あるなあ。楢山節考の世界が近代まで普通だったようなイメージ持たれてしまう。 1970年出版。老人対策、その頃よりは進んでいると思いたい。 上下巻の上2022/03/01
yumiha
57
『100分で名著』における上野千鶴子氏の紹介が歯切れ良く、自分がいかに老いをマイナスイメージでしか捉えていなかったかと反省させられたので、かつて『第二の性』を途中挫折したくせに読んでみたくなった。しか~し‼生物学や歴史の中で語られてきた老いは、マイナスイメージどころか、むごい!悲惨!『リア王』の老いの様子…が、当時の社会の不条理さを描いていたとは…。救いは『レ・ミゼラブル』の老ジャン・バルジャン(80歳!)が若いマルセルを背負って地下道を逃げる場面こそ、ヴィクトル・ユーゴ―が書きたかったのだということ。2022/06/02
ころこ
43
訳が読み易く、人文書にしては一般の本に近い感覚で読めます。上巻では、老いを生物学、民族学、歴史、社会学のそれぞれの観点から考察しています。老いは確かに衰えであるにも関わらず、しかし経験と知恵と安らかさをもたらすものであると擁護します。他方で、冒頭で「私は~」という一人称を使っているのが印象的です。人文学とは人間に対する学であることは間違いありませんが、それは同時に人間の中に否応なく私という存在が入ることでもあります。人間を考えることが究極に自分を考えることになり、自分を考えることが人間を考えることを問い直2021/07/13