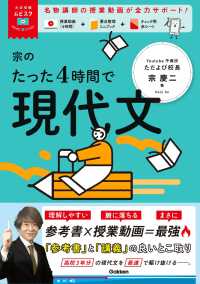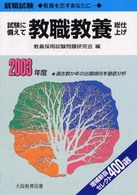内容説明
ネットを介して流れる無数の映像群と、ソーシャル・ネットワークによる絶え間ないコミュニケーションが変える「映画」と社会。「表層批評」(蓮實重彦)を越えて、9.11/3.11以後の映像=社会批評を更新する画期的成果、待望の書籍化。ゼロ年代批評の到達点にして、新たなる出発点。
目次
第1部 環境分析(「映像圏」の誕生;「からだ」が/で見るヴィジュアルカルチャー)
第2部 歴史(映像圏の映画/映像史)
第3部 作品論/メディア分析(作品論―映像圏作家を読む;メディア分析―映像圏のなかのTwitter)
第4部 社会論(映像圏の「公共性」へ―「災後」社会の映画/映像論)
著者等紹介
渡邉大輔[ワタナベダイスケ]
1982年栃木県生まれ。日本大学大学院芸術学研究科博士後期課程芸術専攻修了。博士(芸術家)。専攻は日本映画史・映画学。現在、日本大学芸術学部非常勤講師、早稲田大学演劇博物館招聘研究員。2005年、批評家・東浩紀責任編集のメールマガジン『波状言論』に投稿した「“セカイ”認識の方法へ」で批評家としてデビュー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
35
正直、議論の文脈がよく分からないのですが、著者のデビュー作で、読まれてしまうことの怯えが力みに力み倒した文章の硬さとなって表れているようにみえます。これは、一般の読者に読まれようとしていないな、というのが第一印象です。引用が拡散し過ぎていて、何がどこに書いてあるか分からない、とにかく読者には優しくない本です。業界での評価を気にしているのではないかと推測しますが、むしろ難しい議論を読者に読ませるのが著者の力量ですし、大衆文化なのにこの語り口なのかという疑問と拒否反応だけが残りました。2021/10/29
サイバーパンツ
11
SNSの普及や情報社会化によって、イメージが氾濫した現在の映像環境を「映像圏」と名付け、その映像圏システムをTwitterやニコ動などの現代のメディア環境から過去の映画(批評)史まで広く接続して分析した本。映像文化論かつメディア論として読める。変にペダンチックな文章なので、なかなか頭に入って来ないところもあるが、過視的であるがゆえに不可視となった映像環境とそこにおける掴みどころのないリアリティに輪郭を与えようとしている意欲的な書だと思う。2019/01/07
しゅん
9
現代映像文化の見取り図。「ソーシャルメディア」がもたらす「イメージの氾濫状態」を著者は「映像圏」と名付ける。この「映像圏」の時代を描写していくための下準備としての、環境・歴史・作品の分析。鮮やかな論調が見られないため地味な印象を与えるが、全体性の見えない時代の全体性を探る作業の一環として本書は置かれているからこそ、地道な作業を行っているようにも思える。現代の分析より、初期映画に見られる「健康と病」の問題系の記述が個人的には興味深いな。分析に挙げる作家がウェルズと岩井俊二というのも独特。2017/12/31
鳩羽
4
ソーシャルメディアの利用拡大、社会そのもののソーシャル化によって写真・動画などのイメージの文化は大きく変わった。この、イメージが自由に開かれ氾濫しているような映像環境を映像圏と名付け、映像圏が人々のコミュニケーションと身体的情動生と深く関わっていることを、作品論や映画史とすり合わせて見ていく。…ちょっと興味を持った〜程度で手にとって見たら、とても難しかった。社会学や哲学といった現代思想の用語と、論文みたいな書き方に慣れない一般向きではないのかもしれない。2013/02/26
mittsko
1
文学、映画、テレビからネットへ、現代の映像的想像力になにか変化がありそうだ… 疑いなく重大なこの問いに真正面から取り組む意欲作 幾人かの批評家が本書を推薦していたので、つよい関心をもって精読した しかし、面白い発見はなかったし 何より論旨がよく分からなかった 筆者は、新しい何かがあると言っているのかいないのか? 蓮実流の表層批評を批判しつつデリダ哲学を無批判に採用するのはお門違いではないのか?(この疑問は、ヴィトゲンシュタインの誤読といってよいほどの浅読により強化されるばかりだ)等など がっかりした2015/08/03
-

- 和書
- 幽霊劇場